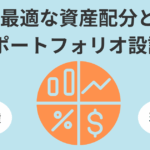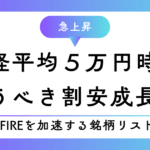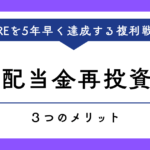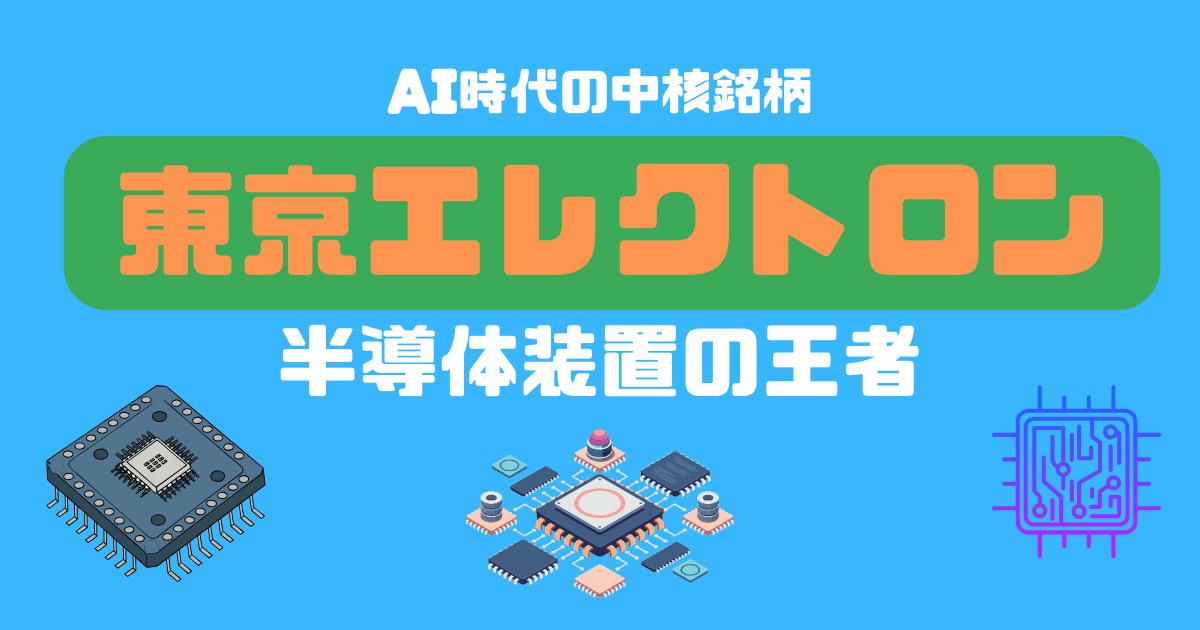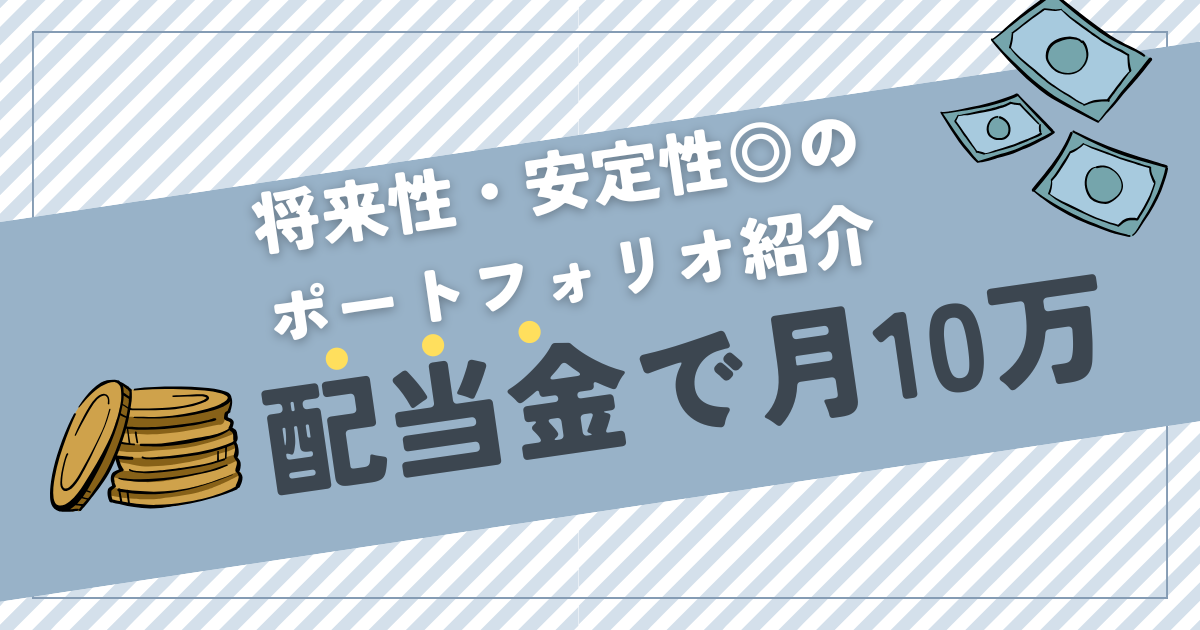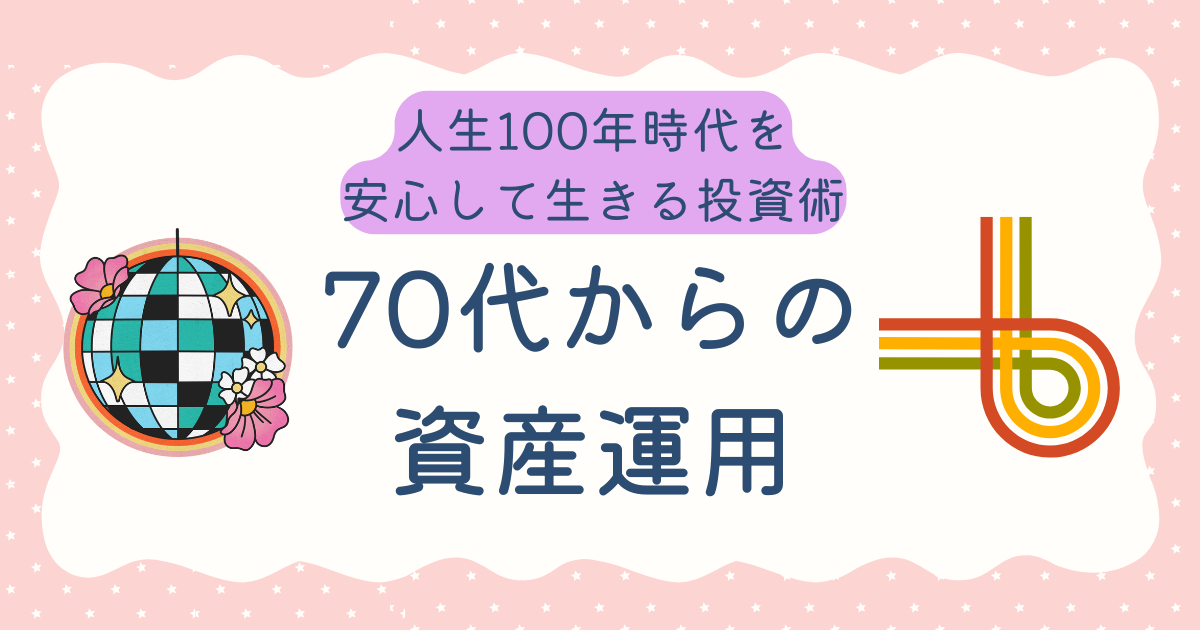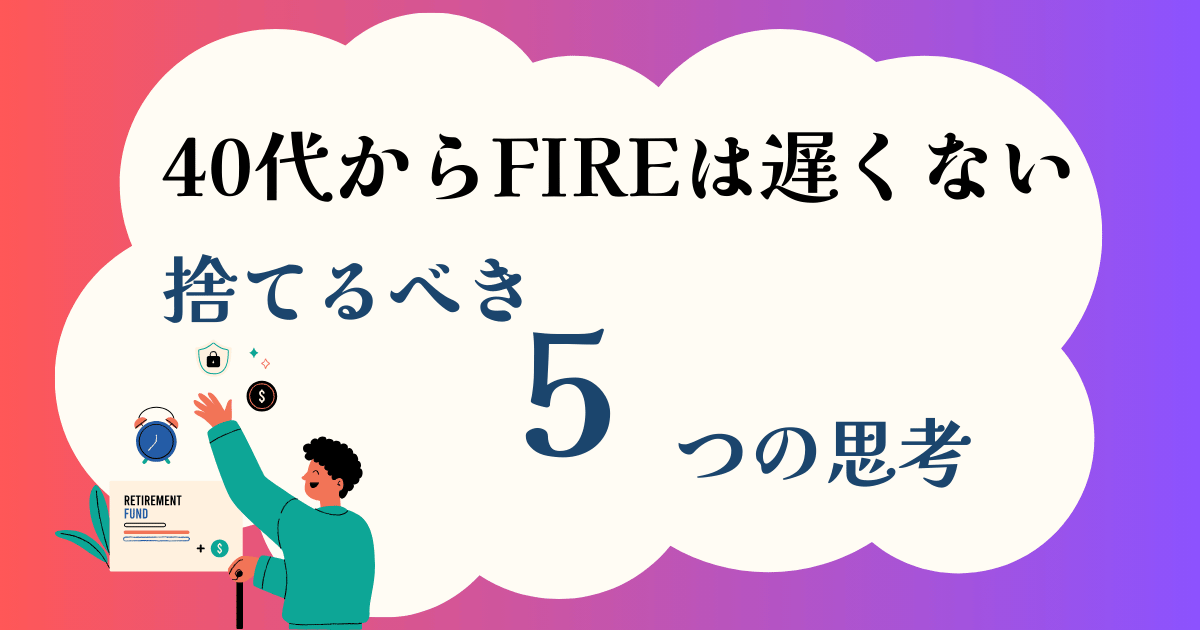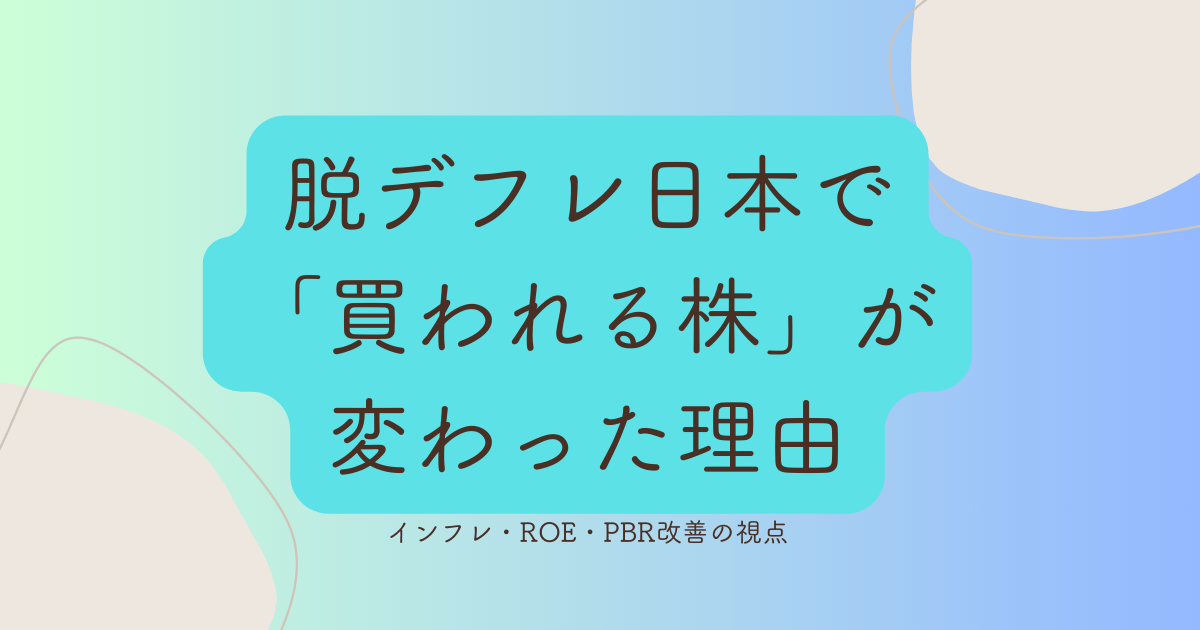はじめに
株式投資や資産形成を通じて早期リタイアを目指す「FIRE(Financial Independence, Retire Early)」という考え方が、日本でも静かなブームを呼んでいます。
特に「フルFIRE」とは、仕事から完全に手を引き、投資運用による不労所得だけで生活を賄う状態を指します。
私も目指しているのは45歳でのフルFIREです。
フルFIREは魅力的ですが、単に「いくら貯めればいいか」を知るだけでは不十分と言えます。
なぜなら、必要な資産額は年齢や家族構成、生活スタイルによって大きく変わるからです。
本記事では、30代、40代、50代の各年代でフルFIREを実現するための資産額を、最新のデータに基づいて具体的に算出します。
その際、国民年金の満額受給を前提とし、厚生年金の加入期間を年代別に差別化(50代が最も長い)して考慮します。
また、人生100年時代ということで、100歳までの長寿を仮定し、総務省の2024年家計調査から得られた平均消費支出を基に、単身、夫婦、4人家族のケースを網羅します。

フルFIREの基本原則:4%ルールと日本の現実
フルFIREの資産額を計算する上で、国際的に知られる「4%ルール」を基盤にします。
このルールは、退職後の年間生活費の25倍の資産を準備し、その4%を毎年取り崩すことで、資産が枯渇せずに30年以上持続可能というものです。
元来、米国の株式市場データを基にしたものですが、日本でもインデックス投資を中心に適用可能です。
ただし、日本特有の低インフレ率(年2%前後)と公的年金の存在を考慮し、調整を加えます。
ここで差別化のポイントは、公的年金を「収入」として差し引く点です。
年金は65歳から受給開始と仮定し、それ以前の期間は資産取り崩しを多く、以降は年金を加味して負担を軽減します。
さらに、100歳までの生存を想定するため、65歳から100歳までの35年間を年金受給期とし、それ以前の期間を追加負担として計算。
インフレ調整として、将来の生活費を年2%上昇と見込みます。
これにより、単純な25倍計算を超えた、現実的な数字が導き出せます。
例えば、30代FIREの場合、年金加入期間が短いため厚生年金が少なく、資産依存度が高くなります。
一方、50代では加入歴が長い分、年金が手厚く、必要な資産が抑えられます。
年代別の年金見込み額:キャリアの積み重ねが鍵
公的年金の額は、FIREの資産負担を左右する重要な要素です。
国民年金は満額(2024年度:月額68,000円、年額816,000円)で統一しますが、厚生年金は平均標準報酬月額43.9万円を基に、加入期間で差別化。令和4年度の厚生労働省データから、平均老齢厚生年金月額を参考に算出しました。
30代FIRE(例:35歳退職)
厚生年金加入10年(25~35歳)。
老齢厚生年金は年額約270,000円(基礎年金加算で総年額1,086,000円)。
早期退職のため、年金頼みが少なく、資産運用が中心となります。
40代FIRE(例:45歳退職)
加入20年(25~45歳)。
老齢厚生年金年額約540,000円(総年額1,356,000円)。
中間的なバランスで、年金が徐々に効力を発揮します。
50代FIRE(例:55歳退職)
加入30年(25~55歳)。老齢厚生年金年額約810,000円(総年額1,626,000円)。
最長加入で年金が最大化され、資産圧縮の効果が顕著です。
これらの額は、平均値に基づく目安ですので、実際には個人の収入履歴で変動します。
家族構成別の生活費:家計調査から読み解くリアル
生活費はFIREの基盤です。
総務省「家計調査(2024年)」の消費支出平均を活用し、税・社会保険料を加味した月額総支出を算出。
単身は住居費が低め、夫婦は共有効率で中間、4人家族は教育・食費で高めとなります。
インフレ調整後、年額に換算しています。
| 家族構成 | 月額総支出(万円) | 年額総支出(万円) | 主な内訳の特徴 |
|---|---|---|---|
| 単身 | 20 | 240 | 食料4.5、光熱・水道2.5、住居3、娯楽2。無駄を削れば抑えやすい。 |
| 夫婦 | 29 | 348 | 食料8.5、交通5、医療・福祉3。共有で効率化余地大。 |
| 4人家族 | 35 | 420 | 食料10、教育6、住居4。子育て期の変動が大きい。 |
これらの数字は全国平均ですが、都市部では住居費が1.5倍になる可能性があります。
ポイントは「平均」を超えない工夫。
例えば、4人家族でも食費の見直しで月2万円削減できれば、資産額が数百万円変わります。
年代・家族別 必要な資産額のシミュレーション
ここでは、上記のデータを統合し、フルFIRE資産額を計算します。
方法は以下の通り:
(1)退職時から65歳までの生活費全額を資産取り崩し(年2%インフレ調整)
(2)65歳以降は年金差し引き後の不足分を資産から(35年間)
4%ルールで運用利回り4%を仮定し、総資産を求めます。
結果は退職時点の必要額です。
30代(35歳)FIREの場合
早期FIREは自由な時間を最大化しますが、年金空白期(30年)が長く、厚生年金10年で年金総額108万円と低いため、資産依存度が非常に高くなります。
| 家族構成 | 年間生活費(万円) | 必要資産額(億円) | 解説 |
|---|---|---|---|
| 単身 | 240 | 0.95 | 年金108万円でカバー率低め(生活費の45%)。月20万円生活で実現可能だが、積極的な投資が必要。 |
| 夫婦 | 348 | 1.37 | 共有生活の効率を活かし、NISAや高配当株(過去に話した2529など)で加速。 |
| 4人家族 | 420 | 1.65 | 子育て費用を考慮。教育資金別準備で、家族の絆を強みに。 |
40代(45歳)FIREの場合
厚生年金20年で年金総額136万円となり、65歳までの20年負担が軽減。
キャリアピークを活かした資産形成が強みです。
| 家族構成 | 年間生活費(万円) | 必要資産額(億円) | 解説 |
|---|---|---|---|
| 単身 | 240 | 0.67 | 年金136万円で負担減(生活費の57%)。趣味や自己投資に余裕が生まれる。 |
| 夫婦 | 348 | 0.97 | 年金がカバー率を上げ、夫婦の健康管理が長期安定の鍵。 |
| 4人家族 | 420 | 1.17 | 子供の独立を見据え、柔軟運用。家族旅行がモチベーションに。 |
50代(55歳)FIREの場合
厚生年金30年で年金総額163万円と手厚く、年金開始までの10年負担が少なく、現実的なゴールです。
| 家族構成 | 年間生活費(万円) | 必要資産額(億円) | 解説 |
|---|---|---|---|
| 単身 | 240 | 0.41 | 年金163万円で生活費の68%カバー。余剰で再投資や寄付を。 |
| 夫婦 | 348 | 0.60 | 夫婦年金で安定。セカンドキャリアの余裕が生まれる。 |
| 4人家族 | 420 | 0.72 | 家族年金効果大。子どもの自立後、ゆとり資金に。 |
各年代を比較すると、FIRE達成のハードルは「退職時の年齢」と「年金加入年数」に大きく左右されることがわかります。
特に30代FIREは、年金空白期間が最長となるため、運用利回りと配当収入の質が生命線となります。
一方、50代FIREでは、長年の厚生年金加入により生活費の6〜7割を年金でカバーできるため、必要資産額は半分以下に圧縮されます。
また、家族構成の違いも明確です。
単身では「ミニマル生活×高配当投資」で比較的早期の独立が可能ですが、夫婦・4人家族では教育費や医療費といった可変支出への対応が鍵となります。
そのため、FIREを計画する際は「年代+家族構成」を軸に、自分に合った戦略を選ぶことが重要ですね。
FIRE実現のための実践ステップ:あなたらしい道筋
数字を知った今、次は行動です。
まずは 家計簿アプリで1か月の支出を“見える化” してみましょう。
実際の数字を把握すると、意外と「減らせるポイント」が見えてきます。
例えば、4人家族の食費が月10万円なら、8万円に抑えるだけで必要な資産額は 約10%も減少。
「支出の最適化」は、FIREへの最短ルートのひとつです。
次に、iDeCoや新NISAをフル活用。
税制優遇を味方につけながら、株式中心のポートフォリオで年4%リターンを狙いましょう。
インフレを上回るリターンを得ることで、資産の“実質価値”を守れます。
さらに、健康寿命を延ばす習慣 も立派な投資。
毎日の散歩や読書など、「長く働ける・動ける体」を維持することが100歳時代の資産寿命を支えます。
そして何より大切なのは、FIREの本質は「お金」ではなく「時間」 だということ。
30代で目指すなら、持たない暮らし=ミニマリズムを。
50代で目指すなら、これまでの経験を“資産”として活かす発想を。
数字の先にある「自分らしい時間の使い方」こそ、FIREのゴールだと思います。
まとめ:FIREは、人生の選択肢を広げるツール
フルFIREの必要な資産額は、30代で単身0.85億円から50代単身0.38億円と、年代で大きく異なります。
家族が増えるほど負担は増しますが、公的年金の支えと家計の工夫で現実的です。
資産形成はマラソンのようなもの。
今日から小さな習慣を積み重ね、自由な未来を手に入れましょう。
関連記事