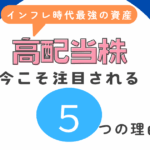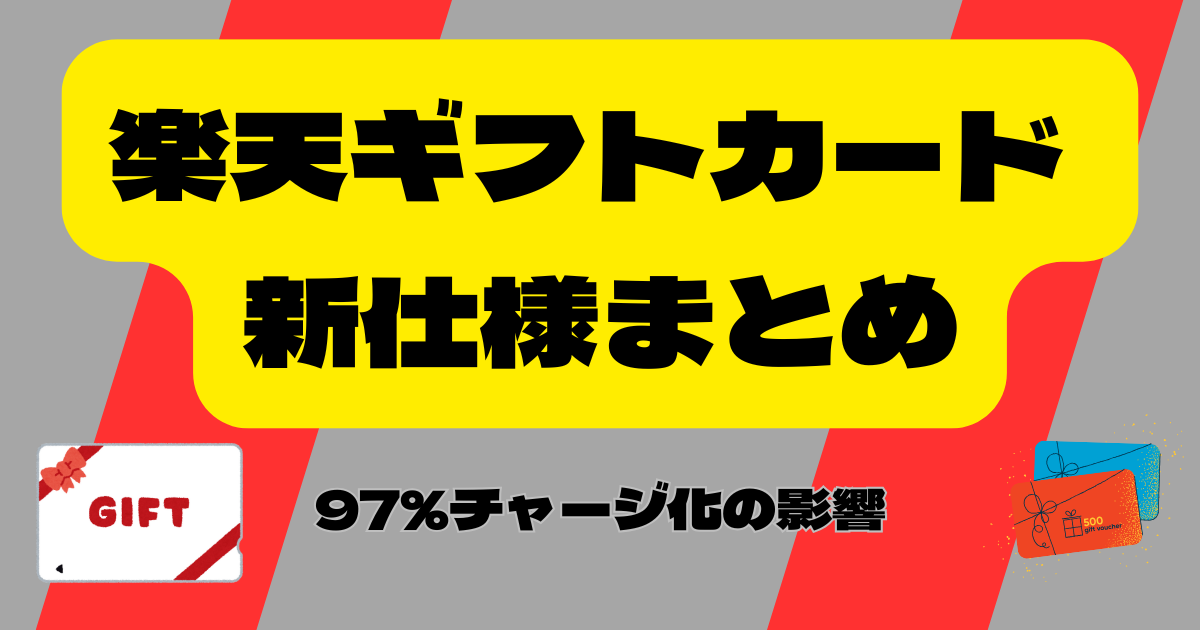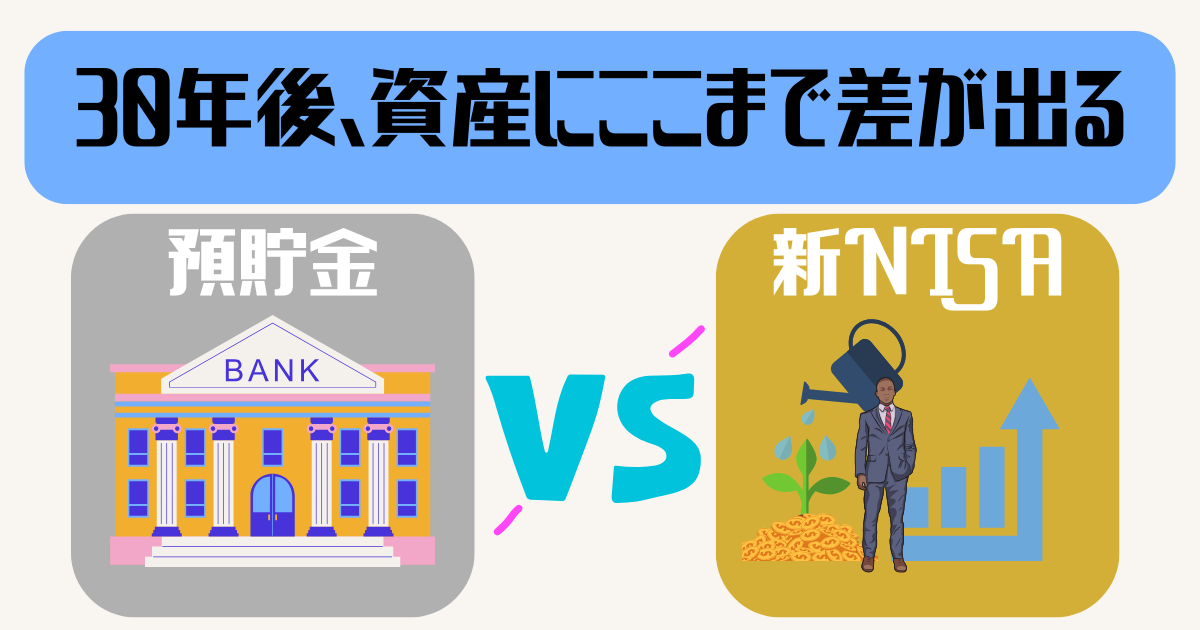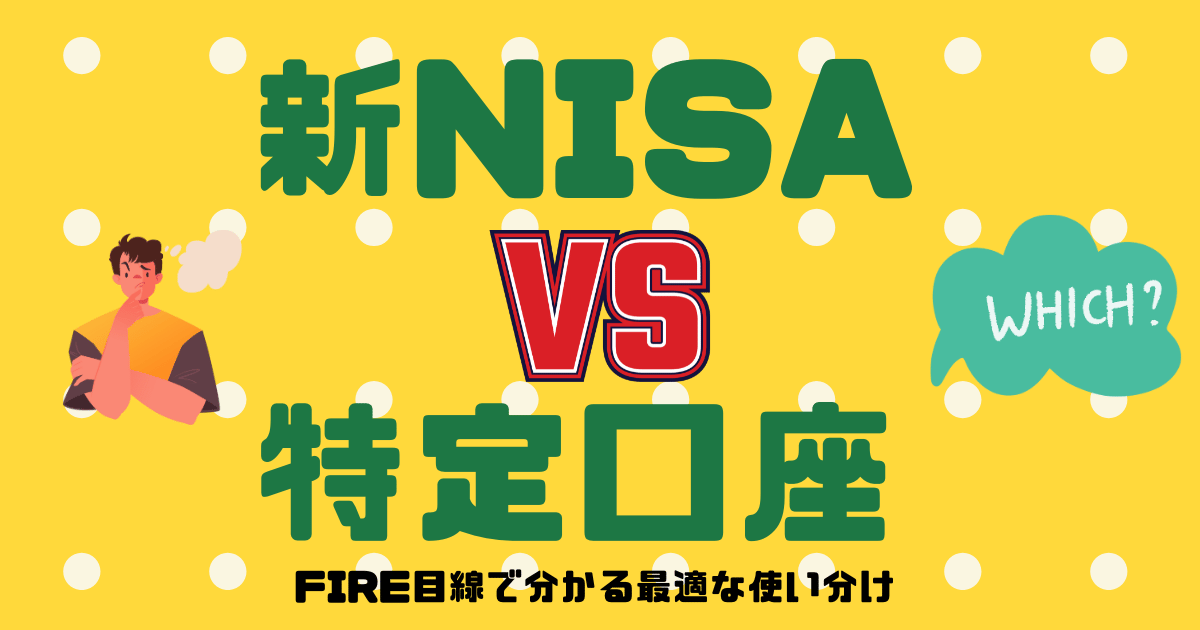投資を始めると、多くの方が安定したリターンをどう確保するのかという悩みに直面します。特に、株式投資やFIREを目指している方にとって、配当金や成長率は大きな関心事になると思います。
今回取り上げるテーマは、「高配当株の7%利回り」と「S&P500の7%リターン」についてです。
数字だけ見ると同じ7%ですが、実際のところ、長期の資産額には驚くほど大きな差が生まれます。その理由は、リターンの質や構造が異なるからです。
この記事では、
- なぜ同じ7%でも将来の資産が違ってくるのか
- 30年後にどれほどの差が生まれるのか
- 暴落局面で強かった高配当株
について解説していきます。
落ち着いた視点で投資を見つめ直すきっかけになりましたら幸いです。
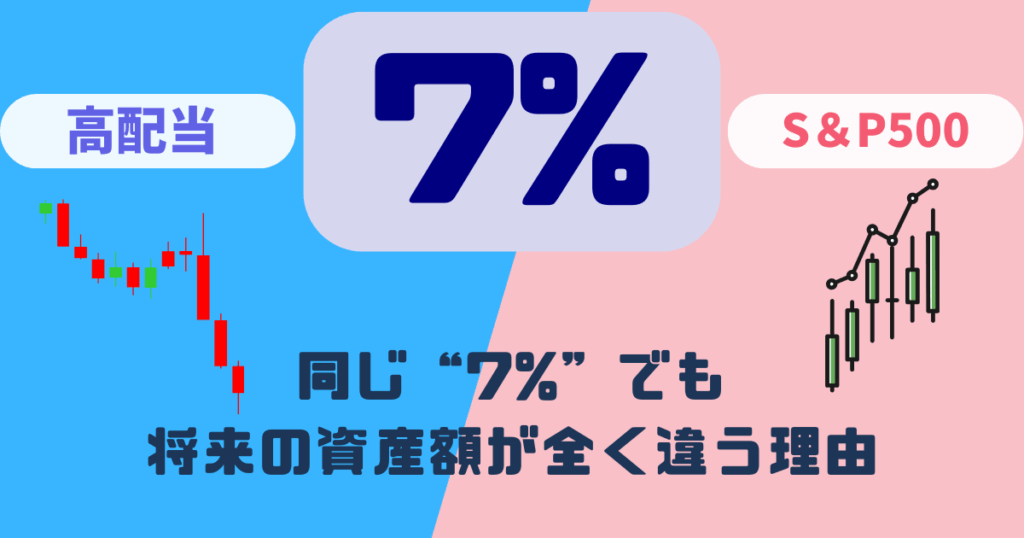
■ そもそも、なぜ“7%”なのか?
多くの投資家が「7%」を基準に考える理由は、次の3つにあります。
1. S&P500の長期実質リターンが約7%前後だから
S&P500の歴史的な平均リターンは「年10%(名目)」と言われますが、ここからインフレ(2〜3%)を差し引くと、実質でおよそ7%前後になります。
そのため、投資の世界では長期的に7%で増えるというのが、一つのスタンダードな目安になっています。
2. FIRE計算で広く使われる“4%ルール”の前提値でもある
FIRE界隈では4%ルールが有名ですが、これは資産が年7%で増えて、3%のインフレがあるという前提で成り立っています。つまりFIREシミュレーションの基礎も 7%成長モデル です。
3. 高配当株の「利回りの上限」に近い数字だから
高配当株の利回りは、安定企業なら3〜5%、高くて6〜7%が一般的です。そのため、比較の際に 「高配当7%」は現実的な上限ライン として扱われることが多いです。
極端な9〜10%利回りの株もありますが、多くの場合は減配・業績悪化のリスクが大きく、比較の基準として適切ではありません。
なぜ同じ7%でも資産額が変わるのか
リターンの“内訳”がまったく異なります
まず初めに確認したいのは、「高配当株の7%」と「S&P500の7%」では、リターンの構造が大きく違うという点です。
■ 高配当株の7%とは
高配当株のリターンは、毎年受け取る配当金の割合が大きい点が特徴です。
株価の成長は年1〜2%程度にとどまる場合が多く(もちろん銘柄によって差はあります)、どちらかというと安定したキャッシュフローを重視した形になります。
- メリット:安定した配当収入が得られやすい
- デメリット:複利の効き方が弱く、資産の増加ペースはゆっくりになりやすい
■ S&P500の7%とは
一方のS&P500は、リターンの中心が株価上昇です。
企業価値の成長がそのままリターンに反映されるため、複利が強く働きます。
- メリット:株価成長が複利を大きく押し上げる
- デメリット:短期的な値動きは比較的大きい
同じ数字に見えても、キャッシュフロー型(高配当株)と資本成長型(S&P500)では、長期運用での伸び方がまったく違ってきます。
30年後、資産額はどれほど差がつくのか
より現実的な前提でシミュレーションします
ここでは、より実務的なリターン構造を反映した前提で計算を行っています。
初期投資:1000万円
合計リターン:年率7%
ただし、高配当株は「5%配当+2%成長」
S&P500は「2%配当+5%成長」
結果は次のようになります。
■ 30年間の資産推移比較
| 年数 | 高配当株(配当中心) | S&P500(成長中心) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 約1,967万円 | 約2,367万円 | +400万円 |
| 20年 | 約3,870万円 | 約5,604万円 | +1,734万円 |
| 30年 | 約7,612万円 | 約13,275万円 | +5,663万円 |
30年後には、約5600万円の差が生まれています。
この差は、配当課税の影響や株価上昇による複利効果が相対的に弱い点など、高配当株の構造的な特徴がもたらすものです。一方、S&P500では企業価値の成長が自然と再投資のように働いてくれるため、複利の積み上がり方が格段に速くなります。インフレを考慮しても、この差は長期でじわじわと広がっていきます。
2025年時点のデータを見ても、S&P500の過去10年平均リターンは年14%超と力強い一方、高配当ETF(VYMなど)は年10%台前半にとどまっています(それでも超優秀ですが…)。この明確な差が、成長の質の違いを物語っています。もちろん、配当を生活の柱にしたい時期もあるはずです。結局のところ、自分が今どの投資ステージにいるかをしっかり見極めるのが肝要です。
暴落局面でも強い高配当株
過去3つの危機を耐えた銘柄とは
高配当株の真価が問われるのは、むしろ暴落時です。
調査対象は以下の3つの局面です。
- 2008年:リーマンショック
- 2020年:コロナショック
- 2022年:ウクライナ危機
株価下落率が市場平均より小さい、配当が維持されていた。この2つを満たした銘柄をランキングにしました。※あくまで私選定基準です。
■ 暴落耐性ランキング(当ブログ選定)
1位:KDDI(9433)
リーマンショックで-15%、コロナショックで-18%、ウクライナ情勢では-12%と、いずれの局面でも下落幅が比較的小さく、通信インフラ事業ならではの安定性が際立っております。さらに23年連続増配を続けており、その強固な事業基盤がうかがえます。
2位:JT(2914)
主要な暴落局面の平均下落率が-16%にとどまっています。嗜好品という性質上、景気変動の影響を受けにくい点が強みであり、リーマンショック時にも配当を維持するなど、株主還元の安定度が高い銘柄です。
3位:三菱UFJ(8306)
下落率が-19%と大手金融機関としては粘り強い動きを見せています。特に金利上昇局面では収益が改善しやすく、環境次第でむしろ追い風が期待できる点が評価されています。
4位:三井住友FG(8316)
海外事業が全体の利益を支える役割を担っており、事業ポートフォリオの広さが下落耐性につながっています。
5位:三菱商事(8058)
資源価格が高騰する局面ではむしろ強さを発揮する時期もあり、総合商社ならではの分散された収益基盤が安定性に寄与しています。
これらの銘柄は、財務基盤が強く、配当を維持する力が高い点が特徴です。
まとめ|目的に合わせて“自分の7%”を選ぶことが大切です
高配当株の7%は「現在の収入を安定させるための利回り」です。一方、S&P500の7%は「将来の資産価値を大きく伸ばすための成長」です。
どちらが正しい/間違っているというものではなく、ご自身の投資ステージによって選ぶべき“7%”は変わってきます。
- 現在の生活を支える収入が必要 → 高配当株が適している
- 将来の資産形成スピードを優先 → S&P500が有力
- 暴落に備えたい → 通信・商社・金融の耐性が高い銘柄が有効
この記事が投資判断の一助になりましたら幸いです。
関連記事