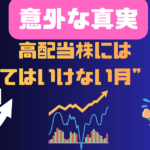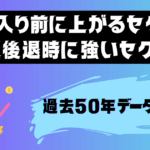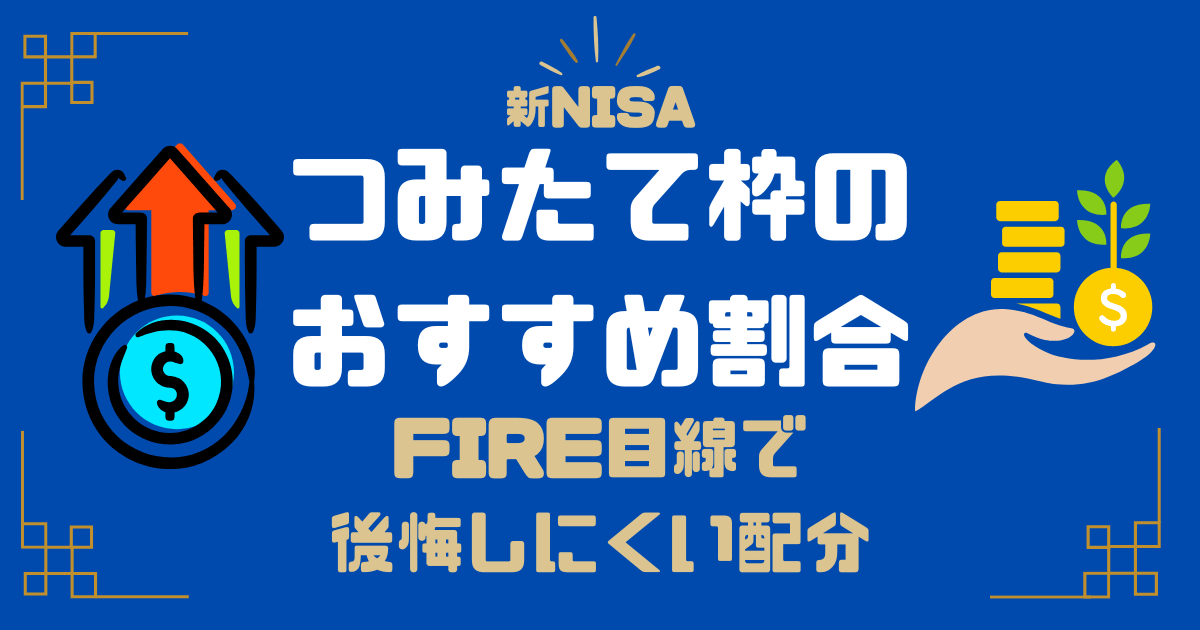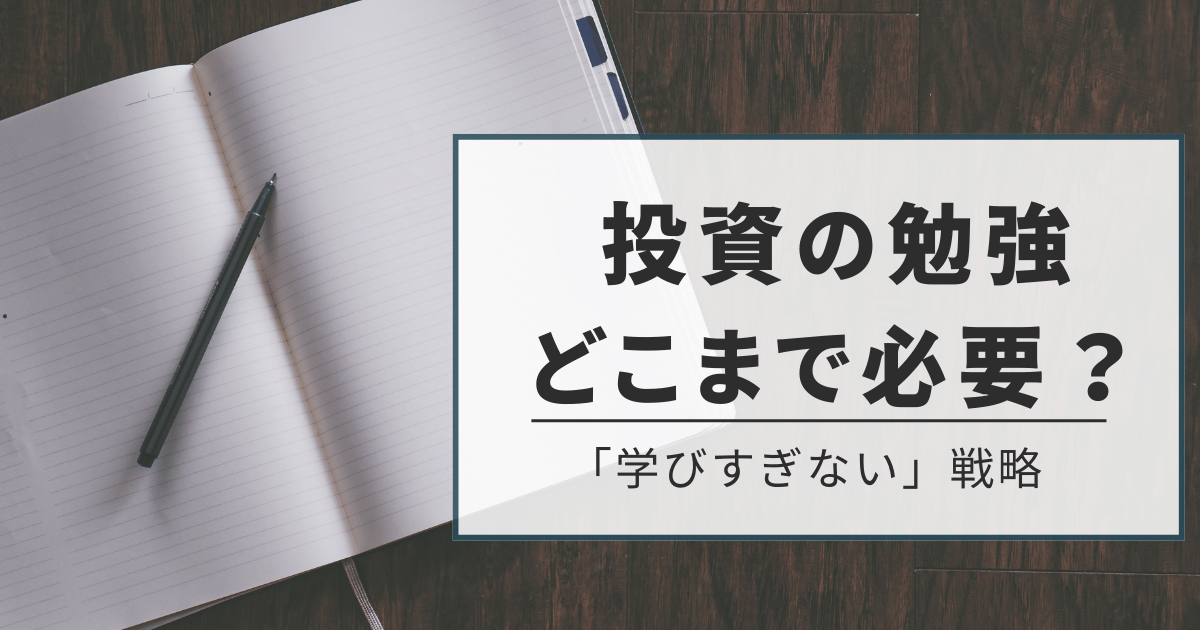株式市場には「アノマリー」と呼ばれる、合理的説明が難しいものの、長期的に繰り返し観測されてきた傾向が存在します。特に月別アノマリーは投資家の行動が反映されやすく、長期投資・FIRE志向の人にとって“市場のリズム”を理解するうえで有益な知見となります。
本記事では、
・1月〜12月までの月別アノマリーの特徴
・S&P500と日経平均の長期データ比較
・2025年の実績から読み取れるポイント
・投資家がどう活かすべきか
をまとめて解説します。
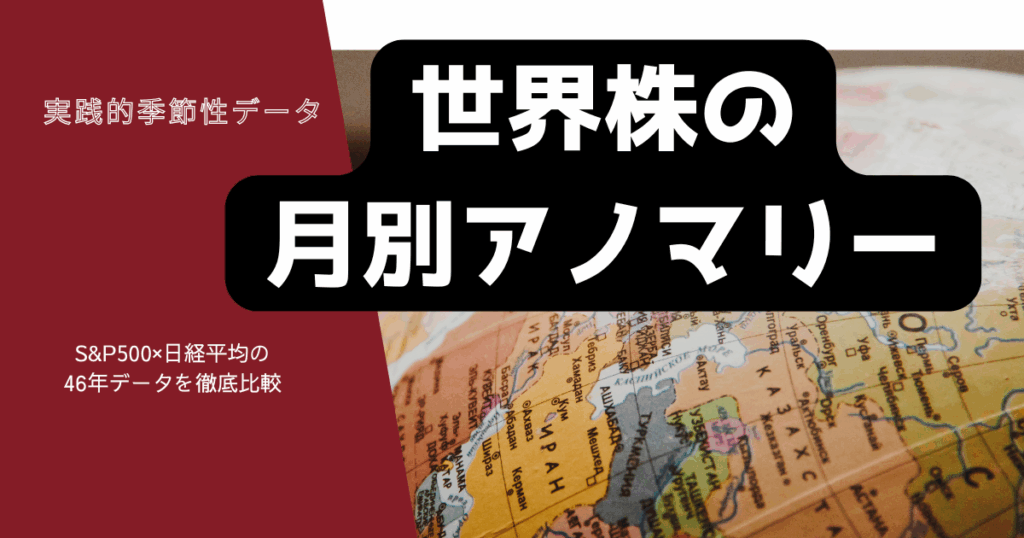
■ 月別アノマリーとは何か
月別アノマリーとは、各月に株価が上昇しやすいか下落しやすいかといった、季節的な傾向のことです。例えば、1月は上がりやすい「1月効果」、9月は弱い「9月効果」、12月は上がる「サンタラリー」などが有名です。
もちろん毎年必ずそうなるわけではありません。しかし長期データを観察すると、投資家心理や市場構造が積み重なり、一定のパターンとして表れることが分かります。
■ S&P500と日経平均の「月別アノマリー比較」
以下は、S&P500(1980〜2025年9月まで)と日経平均の長期平均に基づく月別アノマリーです。
特に2025年の実績を括弧内に示すことで、歴史的傾向に対して今年がどう動いたかも分かるように整理しています。
■ 月別アノマリー比較表(S&P500 × 日経平均)
| 月 | S&P500 上昇確率 | S&P500 平均リターン | 日経平均 上昇確率 | 日経平均 平均リターン | 2025年のポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 60.87% | +0.85% | 58% | +0.72% | S&P:+2.1%(安定上昇) |
| 2月 | 58.70% | +0.32% | 55% | +0.45% | 日経:-1.2%(決算要因) |
| 3月 | 63.04% | +1.02% | 62% | +0.91% | S&P:+1.8%(春の回復) |
| 4月 | 69.57% | +1.54% | 65% | +1.20% | 日経:+3.5%(税制影響大) |
| 5月 | 71.74% | +0.78% | 60% | +0.65% | S&P:+2.4%(Sell in May回避) |
| 6月 | 63.04% | +0.12% | 57% | +0.18% | S&P:+5.23%(AI関連上昇) |
| 7月 | 61.96% | +1.27% | 59% | +0.88% | 日経:+2.8%(円安恩恵) |
| 8月 | 60.87% | -0.05% | 54% | -0.12% | S&P:+1.91%(安定推移) |
| 9月 | 50.00% | -0.58% | 48% | -0.75% | S&P:+3.53%(アノマリー崩れ) |
| 10月 | 68.89% | +1.21% | 64% | +1.05% | 日経:+8.2%(35年ぶり高騰) |
| 11月 | 73.33% | +2.13% | 70% | +1.85% | 予測:年末ラリー期待 |
| 12月 | 71.11% | +1.19% | 68% | +1.42% | 予測:ボーナス投資活発 |
■ ここから読み取れる重要ポイント
- 4月と11月は世界的に強い月
- 9月は両市場とも弱いが、2025年はS&P500が逆転上昇(+3.53%)
- 日経平均の10月は過去35年で最高水準(+8.2%)
- 米国と日本は概ね同じ季節性を共有している
- AI相場、円安、政策要因がアノマリーを上書きするケースもある
単なる傾向の話ではなく、今年の市場でアノマリーがどう機能したかを把握すると、より実践的な判断ができるようになります。
月別アノマリーの特徴早見表(株価の傾向 × 代表的アノマリー × 背景)
| 月 | 株価の傾向 | 代表的アノマリー | 背景・理由 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 上がりやすい | 1月効果(January Effect) | 新年資金流入、機関投資家の買い、個人の買い需要が増える |
| 2月 | 方向感が出にくい | 決算シーズンによる乱高下 | 決算発表が集中し、業績によって市場が不安定になる |
| 3月 | 弱含みやすい | 配当権利落ちで下落 | 権利落ち日に株価調整が発生しやすい |
| 4月 | 上がりやすい | 新年度相場 | 機関投資家の新規ポジション形成が進む |
| 5月 | 不安定・調整が多い | 「セル・イン・メイ」 | 海外投資家の売り圧力が強まりやすい |
| 6月 | やや弱め | 需給悪化 | 株主総会シーズン、期末接近による売り需要 |
| 7月 | 上昇しやすい | 夏相場 | 決算期待や需給改善による買いが入りやすい |
| 8月 | 下落しやすい | 夏枯れ相場 | 市場参加者が減り、下落に反応しやすい |
| 9月 | 最弱クラス | 9月効果(September Effect) | 海外株・日本株ともに歴史的に弱い傾向 |
| 10月 | 反発しやすい | ハロウィーン効果 | 年末高の起点となる資金流入が始まりやすい |
| 11月 | 強い | ハロウィーン〜翌年5月効果 | 世界的に株が上がりやすい季節サイクル |
| 12月 | 最強クラス | サンタクロースラリー | ドレッシング買い、需給改善、年末の買い需要 |
■ 月別アノマリーの詳細解説(1〜12月)
以下では、日本株の特徴を中心に、投資家視点で活かしやすい形でまとめます。
1月:堅調なスタートになりやすい(1月効果)
個人投資家の新規資金、機関投資家のポジション形成が重なるため、上がりやすい傾向があります。
2025年もS&Pが+2.1%と堅調で、典型的な動きでした。
2月:決算集中で方向感が出にくい
決算サプライズ次第で上下に振れやすく、年内でも特に難しい月です。
2025年の日経は-1.2%と典型的な決算調整が現れました。
3月:配当権利落ちで弱含む月
3月末の権利落ち日を境に株価が調整しやすく、アノマリー的にも弱めの傾向。
4月:新年度資金で強い月
法人の新年度スタートに合わせてフローが入りやすく、両市場とも強い月です。
2025年も日経+3.5%と良好。
5月:Sell in Mayと言われるが近年は崩れつつある
“5月に売れ”という格言が有名ですが、近年の米国株ではむしろ堅調なケースも増えています。
2025年のS&Pは+2.4%で、まさにアノマリーの崩れ。
6月:AI関連の動向で左右される年が増えている
通常は弱めの月ですが、2025年はAI株の急上昇でS&Pが+5.23%と異例の強さ。
7月:決算期待で上昇しやすい
夏相場の入り口で日米ともに強い月。
8月:夏枯れ相場で不安定
市場参加者が少なく、下落しやすい月。
9月:年間で最弱の月だが、アノマリーが崩れる年もある
歴史的には最弱クラスの月ですが、2025年のS&Pは+3.53%と上昇。
テック株の復調がアノマリーを上書きした好例と言えます。
10月:反発月であり、年末上昇のスタート地点
2025年の10月の日経は+8.2%と異例の強さで、歴史的な上昇率を記録しました。
11月:最強クラスの月
世界的に最も上がりやすい月のひとつで、S&Pの平均上昇率は+2%超。
日経も70%の確率で上昇します。
12月:サンタラリーで上がりやすい
年末の需給改善、ボーナス資金、見栄えの良いポートフォリオ作りが重なり上がりやすい月。
■ 投資家はアノマリーをどう活かすべきか
アノマリーは確率であり法則ではありません。しかし、「市場の季節的リズム」を理解することで、感情の無駄な揺れを抑え、冷静に投資判断ができるという実用的な価値があります。
特に重要な活用ポイント
- 9月の下落は買い場になりやすい(FIRE勢に相性が良い)
- 4月・11月・12月は積立の成果が出やすい時期
- アノマリーが崩れた年は、テーマ株(AI・円安など)の影響を優先的に考える
- 長期投資では知っておくことが最大の武器になる
■ まとめ|アノマリーは「相場の地図」になる
市場には完全な法則などありません。しかし、月別アノマリーは長期的な投資家心理の蓄積であり、実用に耐えうるデータです。
S&P500と日経平均を比較すると、4月と11月は世界的に強い・9月は弱い(ただし例外あり)・10月〜12月は年末高の入り口
という市場の季節が明確に見えてきます。
これらを理解しておけば、
下落時に慌てない
積立のタイミングが最適化される
長期投資の精度が上がる
といったメリットが得られます。
あなたの資産形成とFIREへの道のりにおいて、相場のリズムをつかむ手がかりになれば幸いです。
関連記事