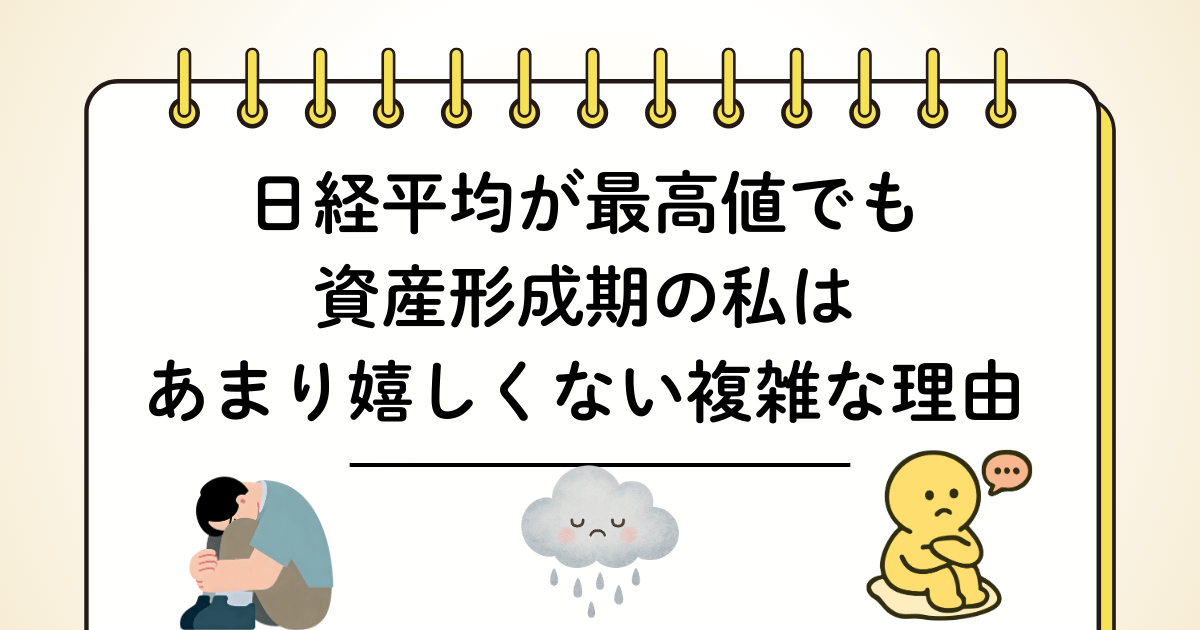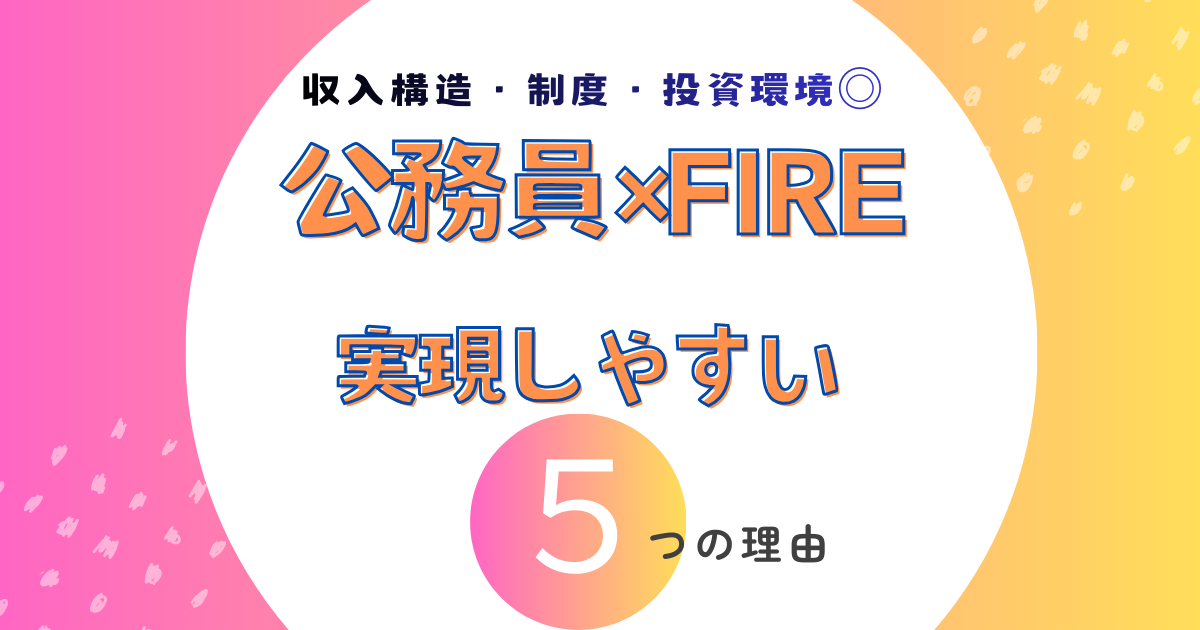「高配当ETFを買いたいけれど、タイミングはいつがいいのだろうか?」投資経験者なら、一度は悩むポイントだと思います。
高配当ETFは安定的な配当収入が期待できる一方で、購入する時期によって投資効率が大きく変わることもあります。
本記事では、高配当ETFの基本から購入タイミングの考え方、そして具体的な戦略について整理しています。
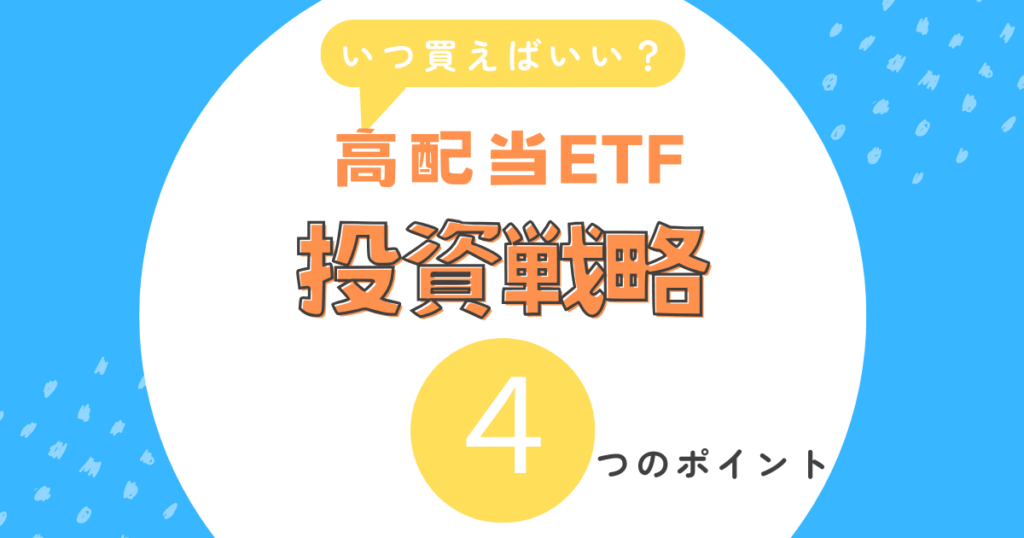
高配当ETFとは?
高配当ETFとは、安定的に配当を出す銘柄を中心に組み入れた株式ETFのことです。
米国株や日本株を対象にしたものが多く、個別株に比べて分散投資が効いているため、リスクを抑えながら配当収入を得られるのが特徴です。
代表的なETFには、米国の高配当株を広くカバーするVYM、高配当かつ財務が安定した企業を中心に構成するHDV、そしてS&P500の中から高配当銘柄を均等配分するSPYDなどがあります。(もはやいにしえのETFとなってきた感があります、私にとっては御三家ETFです。)
いずれも投資家に人気が高く、分散が効いている上に株価の値上がり益と定期的な配当収入が期待できる点で長期投資に適しています。
高配当ETFの注意点
そんな良いとこどりのETFですが、注意点も存在します。
特に配当利回りが高いETFの場合は、利回りが高い銘柄が多く含まれるため、景気後退局面では株価が下がりやすくなることがあり、結果的に一時的な含み損を抱えるリスクがあります。業績悪化が進んでいる企業が混ざっている場合もあります。(リスクとして許容できるのであれば全然OKです。)
高配当ETFは分散効果があるとはいえ、配当だけを見て判断するのではなく、どんな銘柄で構成されているのかを確認し、どのような基準で銘柄が入れ替わるかは把握しておかなければなりません。
高配当ETFの購入タイミングを考えるポイント
では、購入タイミングのポイントについてです。
高配当ETFを買う際に、「いつ買うか」というタイミングの判断は非常に難しいものです。
しかし、いくつかの指標や視点を押さえることで、おおよその目安を持つことは可能です。
①株価の割安・割高を判断する指標
高配当ETFの購入タイミングを考える際には、テクニカル指標のひとつであるRSI(Relative Strength Index:相対力指数)を活用する方法があります。
PERやPBR、ROEなどの代表的な指標がありますが、ETFの買い判断はテクニカル指標のRSIは買い判断として使いやすく、私は楽天証券アプリで、銘柄情報の下に表示させるようにしていて、買い判断に活用しています。
どちらかというと、買わない判断に使うことが多いです。
RSIは株価の「買われすぎ」や「売られすぎ」を数値化したもので、一般的には70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎと判断されます。
短期(14日など)と中期(50日など)のRSIを併せてチェックすることで、過熱感や反発の余地をより正確に読み取ることが可能です。
例えば、短期RSIが30付近で下げ止まり、中期RSIも低下している局面は、長期投資家にとって仕込みの好機となりやすいでしょう。
こうした定量的なシグナルを取り入れることで、感覚に頼らず、冷静に割安水準を判断することができます。
個人的には、銘柄にもよりますがRSIが50を下回ったら買いくらいでもOKだと思います。
②配当利回りと株価の関係を見る
配当利回りと株価は反比例の関係にあります。
株価が下がれば利回りは上昇し、同じ配当額であっても投資家にとって魅力的な水準となります。
利回りが向上したとき、つまり株価下落時は買いのチャンス。(当たり前ですが…笑)
一方で株価が大きく上昇すると利回りは低下するため、焦って購入する必要はありません。
株価が高止まりしているときは積極的に買い増すよりも、定期積立や一時的な待機戦略をとり、無理のない投資がオススメです。
何%の利回りだったら自分にとって買い判断なのか、もしくは下落しても許容できるかを定めておくことで勢い余った買いを防ぐことができます。
③経済・金利動向を考慮したタイミング
高配当株は金利動向や景気サイクルの影響を強く受けます。
特に金利が上昇する局面では、株式市場全体が調整を受けやすく、高配当ETFも例外ではありません。
また、景気後退期には高配当株でも業績悪化が避けられず、株価下落につながるケースがあります。
しかし、このような局面は裏を返せば割安に仕込むチャンス。
経済・金利環境を把握し、景気後退時に一定額を追加投資するなどの工夫を取り入れることで、長期的なリターンを高めやすくなります。
④定期積立(ドルコスト平均法)で定期積立
とはいっても、高配当ETFの購入タイミングを完璧に見極めるのは困難です。
待っていたらスルスルと上がっていくというあるあるも…。
そのため、多くの投資家にとって有効なのが定期積立、いわゆるドルコスト平均法。
毎月一定額を積み立てることで、高値掴みのリスクを減らし、時間をかけて平均取得単価を下げることができます。
また、配当を再投資することで複利効果が働き、長期的な資産形成に大きく寄与します。
個別のタイミングを気にせず淡々と続けられる点は、投資を習慣化する上でもメリットがありますね。
まとめ:無理せず長期視点で買うのが基本
高配当ETFの買い時を考える際には、いくつかの戦略を組み合わせることが有効です。
株価下落時にスポットで買い増しするのは、配当利回りが過去平均より高まった局面で効率的に資産を増やせる方法です。
また、毎月の積立を通じて時間分散を図れば、株価水準に左右されにくく、長期的に安定した投資を続けることができます。
さらに、景気や金利の動向を踏まえて、景気後退期に購入比率をやや高める戦略も、将来の回復局面で大きなリターンにつながる可能性があります。
テクニカル指標を使った判断も、投資家感がでます…(笑)。
とはいえ、買い時を完璧に見極めるのは現実的ではありません。
大切なのは、割安か割高かを判断する指標を持ちつつも、長期的な視点で積立と配当再投資を継続することです。
特に初心者や忙しい投資家にとっては、タイミングを気にせず定期積立を続ける方が、現実的かつリスクを抑えた最適な方法と言えるでしょう。
高配当ETFは、無理なくコツコツと配当収入を積み上げることで、その魅力を最大限に発揮してくれます。
自身の目的、ゴールをしっかり見据え、投資行動に反映させていきましょう。
関連記事