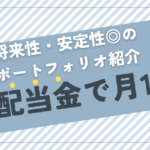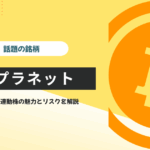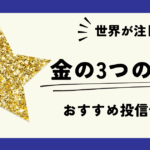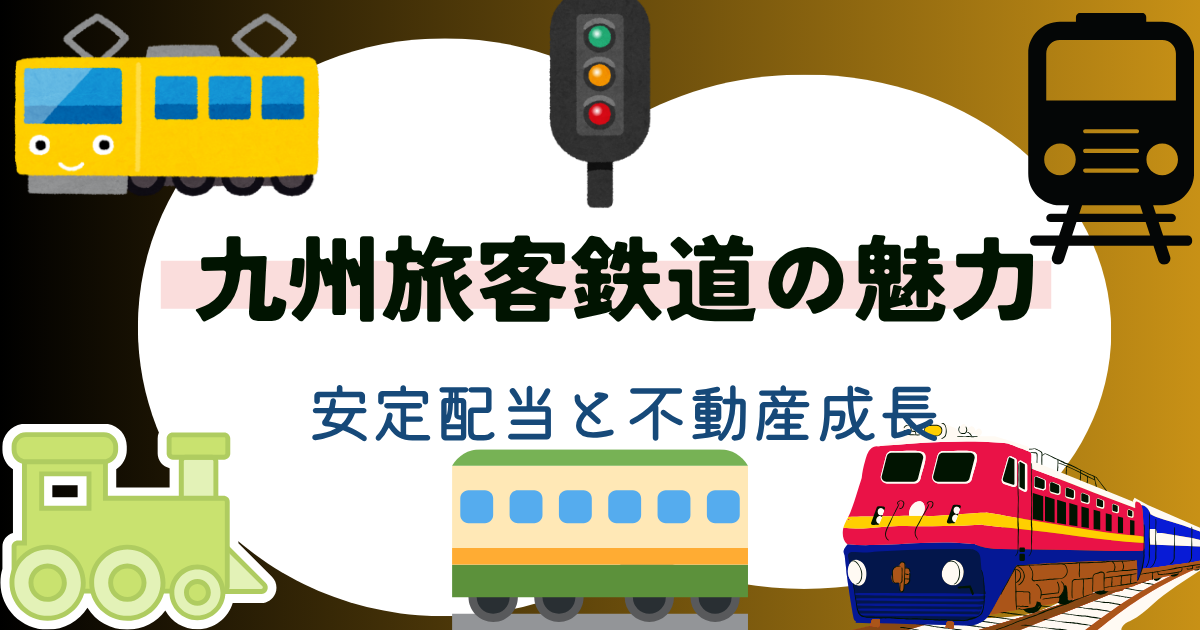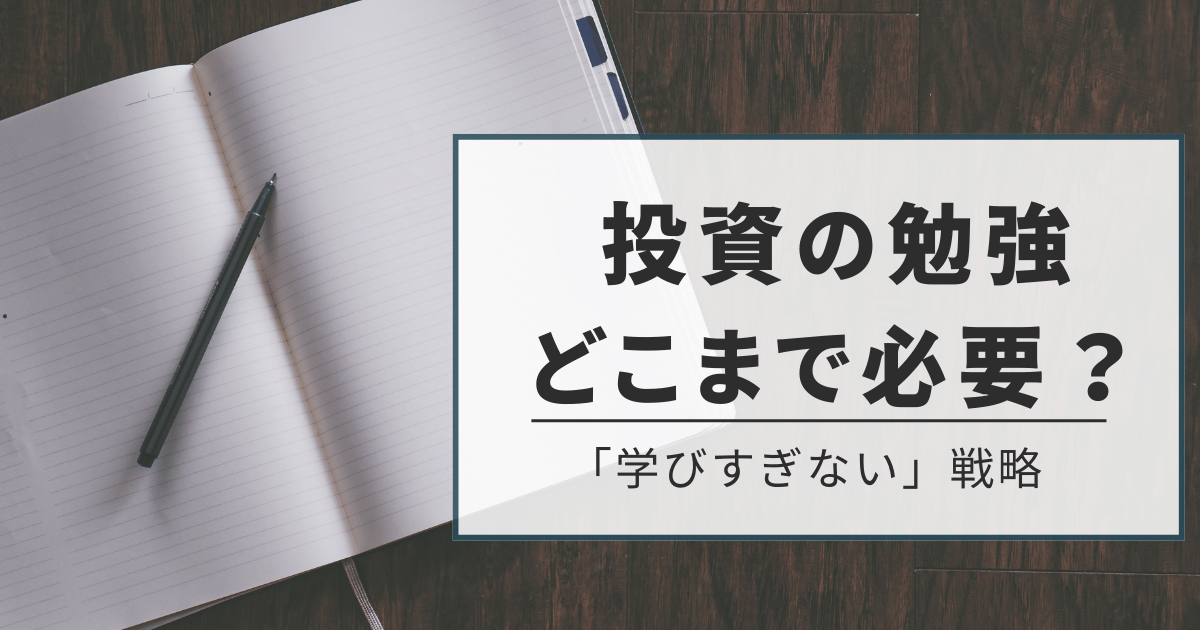最近、AIを活用した資産運用サービス「ロボアドバイザー(ロボアド)」が急速に注目を集め、SNSやニュースでも目にすることが増えました。
株式の銘柄選びやポートフォリオ管理を自動化できるため、投資初心者でも簡単に資産運用を始められるのが人気の理由です。
ちなみに私は以前、AIを活用した投資をやってみたことがあります。
チェックの手間が増えたという理由で手仕舞ったのですが、悪い印象は持つことはなく、むしろ「上手にやりおる…。」と感心したのを覚えています。
ある調査では、個人投資家の10人に1人以上が株式銘柄選びにAIツールを活用しており、半数以上が今後の利用を検討しているとのこと。
そこで本記事では、ロボアドバイザーの仕組みやメリット・デメリット、選び方を初心者向けに解説しつつ、最新ニュースや成功事例、失敗しないための注意点も紹介したいと思います。

ロボアドバイザーとは?
ロボアドバイザーは、AIが投資をサポートしてくれるサービスです。
簡単な質問に答えるだけで、自分に最適な投資商品を診断してくれたり、購入から運用まで自動で任せられます。
2つの種類
- 助言型:投資商品やポートフォリオを提案するだけ。購入や運用は自分で行う。
- 投資一任型:購入から運用、リバランスまでAIが自動で行う。手間がかからず初心者向け。
日本では、ウェルスナビ、楽ラップ、SBIラップ(AI投資コース)、ON COMPASS、THEO+ docomoなどが代表的です。
ロボアドバイザーのメリット
1. 初心者でも簡単に投資できる
質問に答えるだけでAIが最適な商品を提案。
投資知識がなくても運用を始められます。
2. ほったらかし投資が可能(投資一任型)
AIが自動運用してくれるため、購入・運用・リバランスまで手間いらず。
市場の急変にも冷静に対応できます(情が入らないのは機械の強みですね)。
3. 長期投資に向いている
ETFや投資信託を中心とした中長期運用でリスクを分散。
時間を味方にした資産形成が可能です。
それでは、実際の成功例や活用例を見ていきましょう。
成功例から学ぶロボアドの活用法
AIツールで銘柄選定した成功例
元UBSアナリストのジェレミー・ルン氏は、チャットGPTを活用したマルチアセット・ポートフォリオで、従来の高額データサービスと同等の作業を再現しました。
ルン氏が選定した38銘柄は、約55%の値上がりを達成しており、AIを活用した投資の可能性を示す具体例となっています。
個人投資家の利用状況
英国の調査によると、チャットボットやAIを金融アドバイザーとして利用している人は約40%に達しています。
初心者でもAIの力を借りることで投資のハードルが下がり、より多くの人が資産運用に参加できる環境が整ってきています。
市場規模の急拡大
世界のロボアドバイザー市場は、2029年までに2023年比で約600%成長し、約4,709億ドルに拡大すると予測されています。
フィンテック企業や銀行、資産運用会社が続々参入しており、AIによる自動化投資の注目度が急速に高まっています。
ロボアドバイザーのデメリット
1. 手数料がかかる
- 投資一任型:年率1.0%前後
- 助言型:0.33%前後
信託報酬なども別途かかる場合があります。
2. 利益は保証されない
元本保証はなく、相場次第では損失の可能性も。(当然ですが。)
短期で大きな利益は期待できません。
3. 短期投資には不向き
中長期運用向けの設計なので、短期間でのハイリターンは難しいです。
他の資産運用との違い
| 方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 投資信託 | プロが運用 | 手数料抑えめ、自己判断で商品選択可 | 銘柄選びは自己責任 |
| iDeCo | 老後資金向け | 掛金控除など税制優遇 | 60歳まで引き出せない |
| NISA | 投資の税優遇 | 売却益・分配金非課税 | 投資額に上限あり |
| ロボアドバイザー | AIが運用サポート | 手間不要、初心者向け | 手数料あり、短期利益は限定 |
投資信託やiDeCo、NISA、ロボアドバイザーにはそれぞれ特徴があります。
初心者でも安心して資産運用を始められるロボアドを含め、自分の投資目的やリスク許容度に合った方法を選ぶことが、長期的な資産形成の鍵となります。
ロボアドバイザーの選び方
投資一任型か助言型かを決める
先に述べたように、ロボアドバイザーには、投資一任型と助言型の2種類があります。
初心者の場合は、購入から運用、リバランスまでAIに任せられる投資一任型が安心かと思います。
一方で、投資に慣れてきたら助言型を選び、自分で購入・運用をコントロールすることも可能。
自分の投資スタイルに合ったタイプを選ぶことが、失敗を防ぐポイントです。
運用手数料を比較する
運用手数料はロボアドバイザー選びの重要な要素。
投資一任型は自動運用の利便性が高い反面、手数料がやや高めになる傾向があります。
助言型は手数料が安価なサービスも多く、さらに信託報酬も加わるため、総コストを把握したうえで比較することが重要です。
最低投資金額を確認する
少額から投資を始められるかどうかも大切です。
例えば、ON COMPASSは1,000円から投資可能で、まずは少額でAI投資に慣れることができます。
一方、ウェルスナビは10,000円からのスタートですが、分散投資や自動リバランスなど充実した運用が可能です。
自分の資金状況に合わせて選びましょう。
代表的なロボアドバイザーの特徴
楽ラップ(楽天証券)
下落時に価格変動を抑えるDRC機能を搭載。
株式市場が急落しても、債券比率を一時的に増やして下落幅を抑えます。(凄っ…!)
長期的に安定した運用を目指す初心者向けです。
SBIラップ(AI投資コース)
毎月自動でポートフォリオをリバランス。
AIが最適な投資配分を決めるため、ユーザーはほぼ手間をかけずに運用可能です。
ON COMPASS(マネックス証券)
最低1,000円から投資でき、運用手数料も0.9775%程度と割安。
少額からAI投資を試したい人に適しています。
初心者が失敗しないAI投資の注意点
信頼できる情報源を使う
AIツールは便利ですが、すべてのデータにアクセスできるわけではありません。
ペイウォール(有料コンテンツ)の背後にある情報や非公開データにはアクセスできないことがあります。
公式書類やSEC提出資料など、信頼性の高い情報をもとに運用判断を行うことが重要です。
AIは万能ではない
チャットGPTや汎用AIは数値や日付を誤る場合があります。
また、過去のデータや既存のストーリーに頼りすぎて将来を予測しようとするリスクもあります。
生成AIに頼りすぎず、自分自身で確認・判断する姿勢が求められます。
損失リスクを理解する
AIによる運用でも元本保証はありません。
市場が急変した場合、損失が出るリスクは常に存在します。
リスク管理ツールの併用や中長期での運用を前提に投資することが、安定した資産形成につながります。
小額から始める
まずは最低投資金額が低いサービスで少額から始め、AI投資に慣れることをおすすめします。
少額で運用しながらAIの挙動や投資の仕組みを理解することで、より安心して投資を続けることができます。
まとめ
ロボアドバイザーは、初心者でも手軽に資産運用を始められる強力なツールです。
メリット:手間不要、長期投資向き
デメリット:手数料あり、短期利益は限定、元本保証なし
最新ニュースや成功事例を参考に、少額から試し、サービスや手数料を比較して、自分に合ったロボアドバイザーを選ぶことが成功のカギですね。
人間には感情や心があり、どうしても切り離すことがきません。
市場の急変や判断に迷う瞬間もありますが、ロボアドバイザーは感情に左右されず、機械的に最適な資産配分を組み入れてくれる点が大きな魅力です。
感情に振り回されず、効率的に資産運用を進めたい人にとって、心強いパートナーと言えるでしょう。
関連記事
どのようなポートフォリオで何を目指すかは、自分の目的に沿って進めたいですね。
分散投資として金、ビットコインは一考の価値があります。