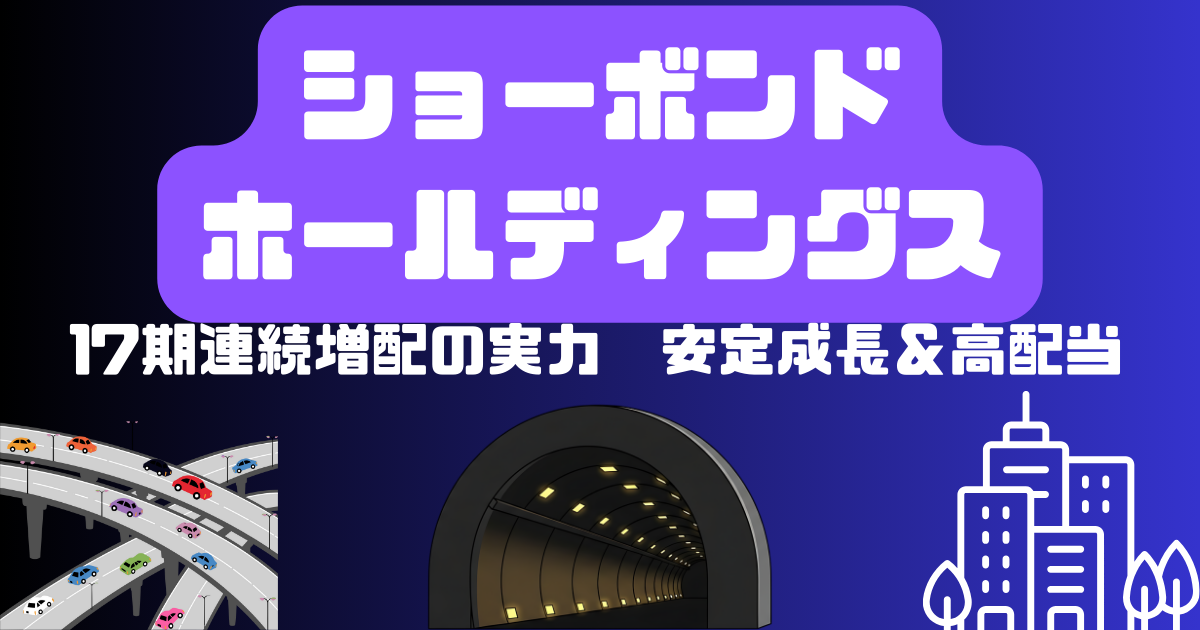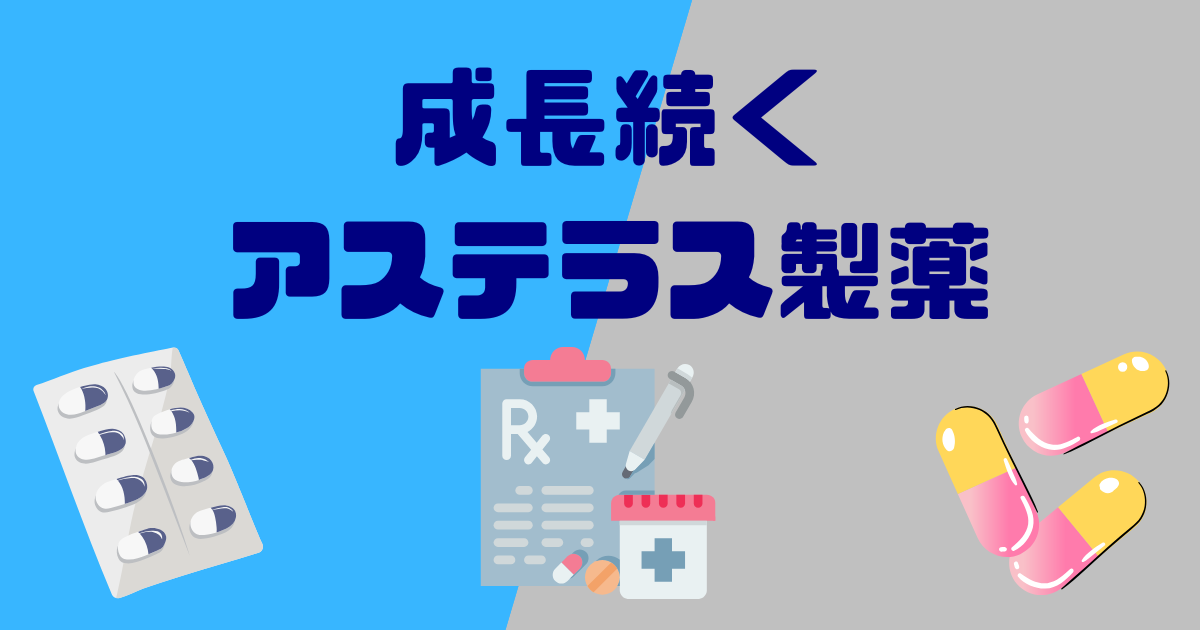高配当株投資を始めたい人にとって、最初のハードルは「どの銘柄を選ぶか」。
個別銘柄を1社ずつ利回りや業績を確認し、配当の安定性や業種の偏りまで考えてポートフォリオを組むのは、時間と手間がかかります。
そんな中で確かな実績と人気を兼ね備えたETFの一つが、上場インデックスファンド日本高配当(1698)です。
このETFは、東証の「配当フォーカス100」に連動する設計で、国内の高配当銘柄を幅広くカバーすることで個別銘柄選定の手間を大きく減らしてくれます。
わずか数千円から購入でき、証券口座一つで国内の高配当株に分散投資できる手軽さは、忙しい個人投資家にとって大きな魅力。
「手間をかけずに安定的なインカムを得たい」というニーズにうってつけで、長期保有で配当を再投資しつつ資産形成を目指す投資家から高い評価を受けています。
まさに、日本の高配当投資の入り口としてふさわしい一本である1698は、そんな役割を果たしてくれる選択肢になります。

上場インデックスファンド日本高配当【1698】とは?
基本概要と運用の仕組み
上場インデックスファンド日本高配当【1698】は、2009年に上場した東証ETFで、アモーヴァ・アセットマネジメントが運用を担っています。
主な投資対象は、東証一部上場企業を中心に選定された100銘柄で、時価総額の大きさと予想配当利回りの高さを基準に構成されています。
この指数は、毎年1月と7月に定期的に銘柄を見直す仕組みを採用しており、市場の変化に柔軟に対応する点が秀逸です。
配当の安定性と魅力
このETFの最大の魅力は、分配金の安定性にあります。
年4回(1月、4月、7月、10月)の分配金支払いが予定されており、直近12か月の実績分配金は1口あたり104.4円。
多くの日本高配当ETFが年4回とはいえ、4月と10月に分配金が偏る傾向があるのですが、1698は偏りがほとんどありません。
現在の株価3,320円で換算すると、利回りは約3.14%となりますが、増配実績(後述)素晴らしく、将来的には4%、5%に達する可能性が大いにあります。
最新データから見る【1698】の割安感
PER・PBRから読み解くバリュエーション
2025年10月15日時点で、【1698】が連動する「東証配当フォーカス100指数」の予想PERは約12.5倍、PBRはおよそ1.1倍となっています。
これは同時期のTOPIX平均(PER約15倍、PBR約1.4倍)と比較しても、明らかに割安な水準といえます。
つまり、市場全体と比べて利益に対して株価が低く評価されているということ。
加えて、PBR(株価純資産倍率)も1倍前後と、企業の保有資産価値に対しても過度に買われていない、堅実な銘柄群で構成されていることが分かります。
このように、「東証配当フォーカス100」は配当利回りだけでなくバリュエーション面でも魅力的な指数であり、割安・高配当という二つの条件を兼ね備えたポートフォリオを形成できるのが1698の大きな強みです。
構成銘柄上位10社の分析
安定と成長を両立する企業群
| 順位 | 銘柄名 | コード | 比率 (%) | 主な特徴(予想配当利回り) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 6.47 | メガバンク、金利上昇恩恵、利回り3.8% |
| 2 | 日本たばこ産業 | 2914 | 8.05 | たばこ・医薬、安定キャッシュ、利回り5.1% |
| 3 | 中外製薬 | 4519 | 5.64 | バイオ医薬、成長株寄り、利回り2.8% |
| 4 | ブリヂストン | 5108 | 5.53 | タイヤメーカー、耐久消費財、利回り3.1% |
| 5 | トヨタ自動車 | 7203 | 5.95 | 自動車大手、グローバル展開、利回り2.5% |
| 6 | キヤノン | 7751 | 6.00 | 精密機器、イメージング、利回り3.0% |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 3.66 | 金融サービス、多角化、利回り3.6% |
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 2.70 | メガバンク、安定配当、利回り3.9% |
| 9 | INPEX | 1605 | 3.09 | エネルギー探鉱、資源価格連動、利回り4.2% |
| 10 | 三菱商事 | 8058 | 3.03 | 総合商社、リソース投資、利回り3.4% |
この表から読み取れるのは、【1698】の「差別化された分散効果」です。
たとえば、トップの三菱UFJや日本たばこ産業は、景気後退時でも揺るがないディフェンシブ性を発揮しますが、中外製薬やトヨタ自動車の組み込みにより、ヘルスケアや自動車セクターの成長ポテンシャルを加味。
こうした銘柄シフトは、単一セクターETFのボラティリティを抑え、心理的な安心感を生み出します。
セクター別構成:ディフェンシブと成長の絶妙なブレンド
ディフェンシブ×成長セクターの調和
【1698】のもう一つの強みは、セクター配分のバランスにあります。
東証33業種分類に基づく最新の内訳(2025年9月30日時点、アモーヴァ・アセットマネジメント月次レポート)を見ると、株式全体の89.15%がエクイティに割り当てられ、残りは現金等です。
トップセクターは銀行業の14.77%で、金融セクターの安定性を象徴しますが、食料品(10.57%)や医薬品(8.32%)のディフェンシブ分野が続き、景気敏感株の過度な集中を避けています。
一方で、輸送用機器(9.36%)や卸売業(7.02%)が入ることで、経済回復時のアップサイドを確保。
以下に上位10セクターを表でまとめました。
これにより、全体のボラティリティを抑えつつ、配当の質を高めている点が際立ちます。
| セクター名 | 比率 (%) | 主な特徴と投資的示唆 |
|---|---|---|
| 銀行業 | 14.77 | 金利上昇で利益拡大、配当基盤堅調 |
| 食料品 | 10.57 | 必需品セクター、インフレ耐性高 |
| その他(REIT含む) | 9.63 | 不動産等で分散、多様な収入源 |
| 輸送用機器 | 9.36 | 自動車中心、グローバル成長期待 |
| 医薬品 | 8.32 | イノベーション駆動、長期安定 |
| 卸売業 | 7.02 | 商社等、サプライチェーン強靭 |
| 電気機器 | 6.72 | 電子部品、技術革新の恩恵 |
| ゴム製品 | 6.61 | タイヤ等、耐久財の安定需要 |
| 鉱業 | 3.09 | エネルギー資源、価格変動対応 |
| 機械 | 2.70 | 産業機械、景気敏感だが配当優良 |
このセクター構成は、単なる高配当追求ではなく、「持続可能なキャッシュフロー」を重視した設計を物語ります。
たとえば、銀行業と医薬品の組み合わせは、FIRE投資家にとって理想的な「守りと攻め」の両立です。
私がポートフォリオに取り入れる際の気づきは、こうした分散が、2022年のような市場調整時でも分配金を維持した点にあります。
上記以外セクター(残り約21%)には通信や建設などが含まれ、全体として東証平均を上回る安定性を発揮。
ETFということで決して派手さはありませんが、こうした細やかな配慮や安定性は、長期投資の土台を築く上で非常に重要です
歴史的な分配金実
1698の分配金は、指数の優良銘柄選定により、長期的に着実な成長を示しています。
アモーヴァ・アセットマネジメントの公式情報に基づき、過去の分配金履歴を年別合計でシンプルにまとめました(データは2025年10月時点の最新値で、1口あたりの円建て額)。
2009年の上場以来、分配金は景気変動を乗り越え、平均年3%以上の増加を続けています。
たとえば、2020年のパンデミック下でも合計約90円を維持し、2024年には104円超へ到達。
こうした推移は、単なる数字ではなく、企業の実力と指数の耐久力を物語るものです。
FIREを目指す私にとって、この安定したキャッシュフローは、再投資の原動力となり、複利効果を最大化する鍵となっています。
| 西暦 | 年間合計 (円) |
|---|---|
| 2009 | 76.1 |
| 2010 | 79.5 |
| 2011 | 83.0 |
| 2012 | 87.3 |
| 2013 | 93.1 |
| 2014 | 99.1 |
| 2015 | 103.3 |
| 2016 | 106.4 |
| 2017 | 111.8 |
| 2018 | 114.8 |
| 2019 | 117.0 |
| 2020 | 113.4 |
| 2021 | 119.1 |
| 2022 | 124.1 |
| 2023 | 129.1 |
| 2024 | 134.4 |
| 2025 | 33.5* |
【1698】の運用実績とリスク
トータルリターンと安定性
過去の運用実績を振り返ると、1698は2009年の上場以来、年平均トータルリターン(配当込み)が約6.5%を記録しています。
これは、TOPIX連動ETFの5.2%を上回る数字で、特に2020年代の低金利環境下で光りました。
分配金の推移を見ても、2019年の1口あたり90円から2024年には104円へ増加しており、企業側の増配トレンドが指数に反映されている証左です。
ただし、リスクを無視できません。
株価は市場全体と連動するため、2022年のような調整局面で10%以上の下落を経験しました。
それでも、PBRの低さから回復が早く、配当再投資派にとっては「安く買える機会」となります。
高配当ETFを「受け身の投資」と見なす人が多い中、1698は「アクティブな資産形成ツール」として機能します。
たとえば、NISA成長投資枠の対象銘柄であるため、非課税で長期保有が可能。
FIREを目指す私のように、毎月の分配金を生活費に充てつつ、余剰分を再投資すれば、複利の魔法が加速します。
市場が過熱する今、こうした商品は「守りの投資」の象徴。
短期売買の疲弊から解放され、ゆとりある資産形成の喜びを実感できるのではないでしょうか。
まとめ:【1698】がもたらす“生活に還元される投資”
上場インデックスファンド日本高配当【1698】は、
- 割安な評価指標
- 安定した配当と構成銘柄
- 絶妙なセクターバランス
これら三位一体の強みを兼ね備えたETFです。
資産形成の旅は、一歩ずつ。実に前進いたしましょう。
関連記事