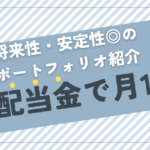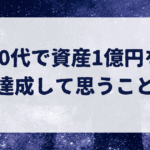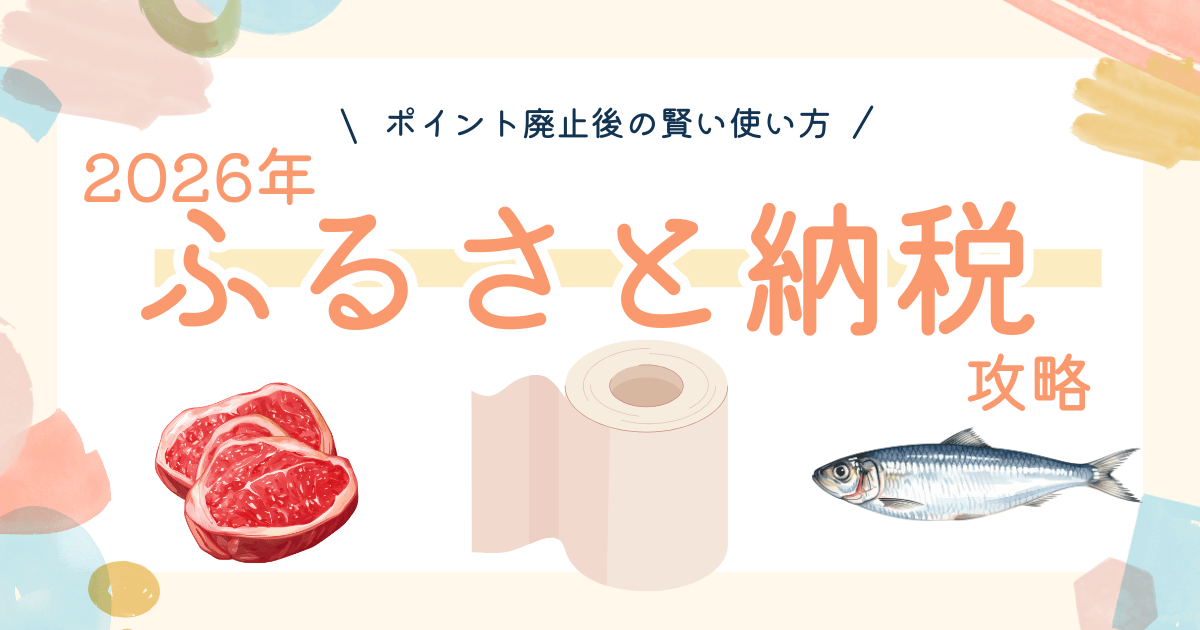誰しも、過去に一度は株の世界で何かしらの失敗を経験しているのではないでしょうか。
かくいうサラリーマン投資家の私は、数えきれないほどの失敗をしてきました。
「億り人」と呼ばれる富裕層に到達したとはいえ、その道のりは決して順風満帆ではありませんでした。
投資を始めたばかりの頃は、どうしても「失敗」から学ぶことが多いものです。
しかし、振り返ると共通点が見えてきます。
この記事では、投資初心者が特にやりがちな5つの失敗と、その回避策を実体験を交えて解説します。
これから投資を始める方や長期投資の際の参考になれば幸いです。
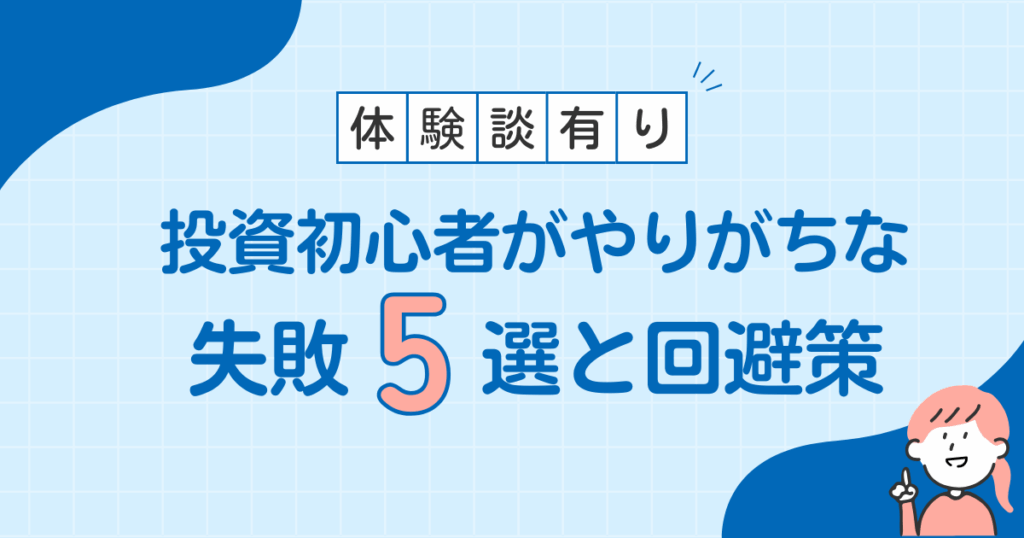
1. 複雑な毎月分配型ファンドに手を出してしまう
私の大きな失敗の一つは、毎月分配型の投資信託に手を出してしまったことです。
当時「毎月お小遣いのように分配金がもらえるなんで最高じゃん」と思い込み、ランキング上位で人気のあったワールド・リート・オープンという投資信託を購入しました。
しかし実態は毎月分配型ファンドの典型で、実際の収益(配当や値上がり益)だけでは分配を賄えず、不足分を元本払戻金(特別分配金)で補う=実質タコ足配当という仕組み。
見かけ上は安定した分配が入ってきますが、その多くは自分の資金を返してもらっているだけに過ぎず、長期的には基準価額が下がりやすい構造になっていました。
気づけば資産はじわじわと減っていき、「分配=安心」という考えは大きな誤解だったと痛感しました。
回避策はシンプルで、「理解できないものには投資しない」こと。
これはウォーレン・バフェットも繰り返し強調している鉄則です。
2. 高利回り銘柄に飛びつく
「高配当だからお得」と思い込み、PSEC(Prospect Capital Corporation)という高利回り銘柄に投資したことがありました。
当時は年利10%以上という数字に惹かれ、毎月1万円以上のキャッシュフローを得て「これは理想の投資だ」と安心していました。
しかし実際は株価がじわじわと下落傾向にあり、さらに減配が発表。
結局、株価の下落と将来性の不安から売却に踏み切ることになりました。
トータルではわずかにプラスで終えられたものの、毎月の配当金という“目先の果実”にとらわれた結果、長期で見たトータルリターンは決して高くはありませんでした。
この経験から学んだのは、配当だけに目を奪われず、株価の成長性や企業の安定性も見るべきということです。
回避策は、配当利回りだけではなく「財務健全性」や「事業の持続性」を見ること。
高すぎる配当はリスクの裏返しである場合が多いです。
米国ETFのVYMやHDVなど、安定配当を長期に渡って維持している銘柄を中心にする方が安心だと言えます。
3. 目先の利益で売却してしまう
ゼンショーホールディングスを購入したのは2013年頃、投資額は約100万円でした。
有難いことに株主優待として、半年ごとに1万円分の食事券もいただけるので、当時は夫婦で「はま寿司」に通い詰めていました。
ところが、あまりにも頻繁に寿司を食べ過ぎて、“寿司に飽きる”という事態に(笑)。
更には株価も順調に伸び、50万円ほどの利益が乗ったタイミングで「もう(色んな意味で)十分だ…」と考えて売却しました。
その時は200万円近くまで上がっていたので、投資としては成功したと思っていたのです。
しかしその後、ゼンショーの株価は驚くほど成長し、2025年現在では当時の投資額100万円が950万円以上に膨らんでいます。

もしあのまま長期保有を続けていれば、単に資産が大きく増えていただけでなく、今もなお株主優待で家族揃って寿司の外食を楽しむことができていたはず。
短期的な利益に満足してしまったがために、結果的には大きなチャンスを逃したと痛感しました。
回避策として学んだのは、目先の利益や一時的な感情に左右されず「長期視点」で投資を続けること。
株式投資は数年〜数十年単位での成長を前提にした方が、成功確率が圧倒的に高くなります。
4. 分散不足で偏った投資をしてしまう
ある時期、利回りの良さに惹かれて、Jリート銘柄ばかりを買い集めていたことがありました。
今から約10年前のことで、当時は平和不動産リートや大江戸温泉リート、さらに現在の日本都市ファンドに統合された日本リテールファンドなどを多く保有していました。
確かにJリートは高い分配金を出してくれるので、毎月や毎期のインカムゲインは魅力的でしたし、配当再投資をすれば資産形成のスピードも上がるように感じていました。
しかし、その裏ではキャピタルゲイン(値上がり益)がほとんど得られず、むしろ微増か微減という状態。
結果として、トータルリターンは思ったほど伸びず、効率的な投資とは言えませんでした。
幸い、損失が出る前に大型株や安定した高配当株へ切り替えることができたため大きなダメージは避けられましたが、もしそのままJリート中心のポートフォリオを続けていたら、マーケット環境の変化や金利上昇局面で大きな損失につながっていた可能性もあります。
この経験から、「高利回り=安心」ではなく、インカムとキャピタルのバランスを見てトータルで考えることが大切だと学びました。
5. SNSで話題の商品に流される
以前SNSで話題になっていた高配当ETF、たとえばQYLDやS&P500カバード・コール版のXYLDなどを、当時は「みんなが買っているから安心」と思い込み、深く仕組みを理解せずに購入してしまったことがあります。
毎月の分配金は魅力的で、確かにキャッシュフローをブーストしてくれる銘柄ではありましたが、私の投資目的である45歳でのFIREや長期資産形成には不向きでした。
もちろん、QYLDやXYLD自体が悪い商品というわけではなく、今でも一部は保有しています。
ただ、話題に乗って何となく購入した結果、自分の投資方針や目指す生き方と合った銘柄を選べていなかったことが課題でした。
この経験から痛感したのは、人の真似だけで投資をするとリターンの損失や思わぬリスクに繋がるということです。
分配金が高くても、自分の息がかからない銘柄はチェックも甘くなり、株価上昇の取りこぼしや想定外の損失につながる可能性があります。
回避策として学んだのは、投資先は必ず自分の目的や目標、ライフスタイルに合ったものを選び、理解して納得した上で購入することです。
SNSやネット上の情報はあくまで参考として活用し、公式資料やファクトシートなどの一次情報で判断することが、長期で安定した資産形成につながります。
まとめ:失敗を活かして長期投資を続けよう
私自身もそうだったように投資初心者が陥りやすい失敗は、いずれも知識の偏在、短期志向、そして情報を無批判に受け入れる無自覚さに起因しています。
しかし、失敗は避けられぬものであり、そこから学び、経験を昇華させて次の成功につなげることの方が重要です。
投資はマラソンのようなもの。
焦らず、地道に、過去の過ちを糧にしながら、長期的な視点で歩みを積み重ねることが、成功への近道です。
もし、みなさんの失敗談があればコメント欄で教えてください…学ばせていただきます!
関連記事
現実的な方法で月10万円の配当金を得る、初心者の方にもおすすめのポートフォリオを提案しています。
理解できないものに投資はしないという、投資の神様の原則に早く出会いたかった…。
現在の利回りが低くても、将来的に高配当になるVYMなどの銘柄は誰にでもオススメできます。
32歳でアッパーマス層に到達したときの気付きです。
その数年後、億り人になることができました。