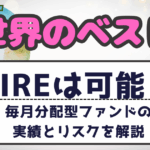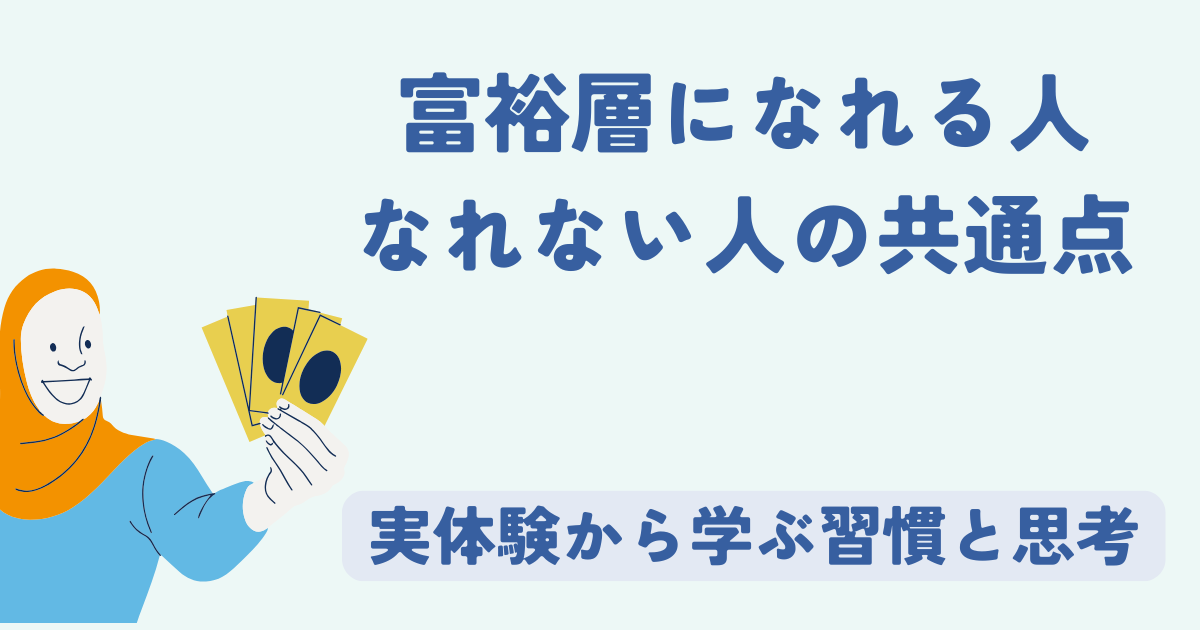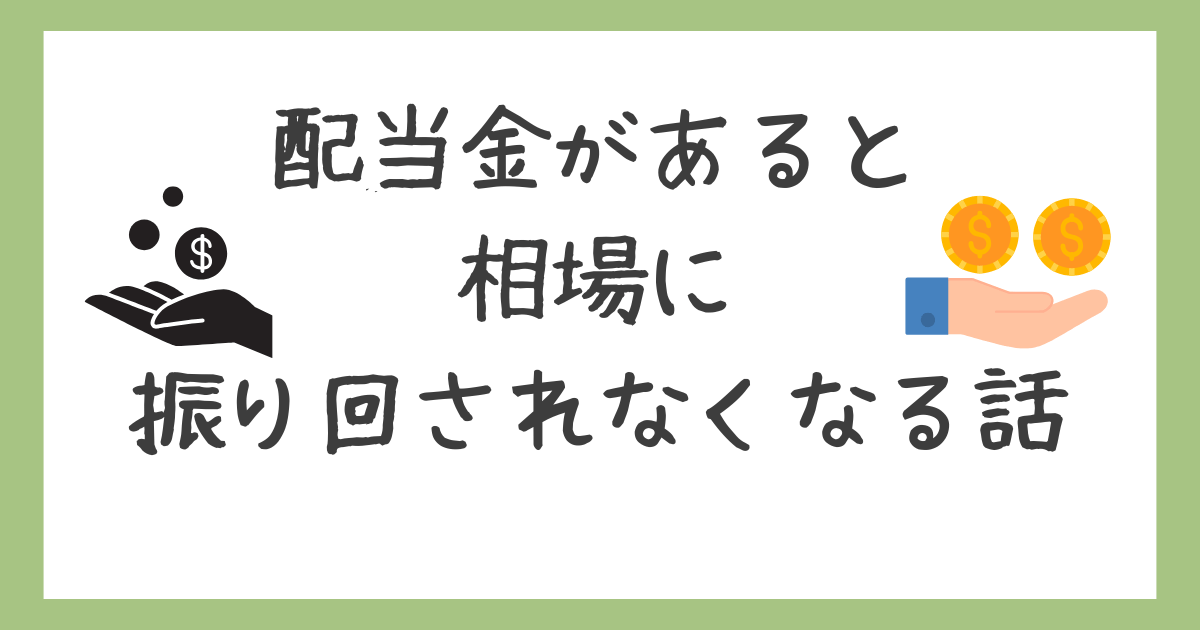JEPQはNASDAQ100に連動しつつカバードコール戦略を組み合わせた高配当ETFです。
利回りは約10%と非常に高く、毎月分配されることから「配当金生活」の夢を描ける銘柄として注目されています。
私も400株弱保有しておりまして、これまでに50万円程度の分配金(税引き後)を頂いております。
さらに凄い点は含み益も60万程度出ているんですよね。
超高配当株にありがちな、株価漸減といった傾向とは真逆の推移で、さすがは世界一の資金流入額を誇るアクティブETFといったところです。
では、そんなJEPQは実際にどのくらいの投資額で生活費を賄えるのか、そしてどのようにリスクを分散するのが現実的なのか。
本記事では、JEPQの分配金実績や上位構成銘柄、必要資産のシミュレーション、さらには分散投資の具体例まで解説します。

JEPQとは?
JEPQ(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)は、NASDAQ100のハイテク株を中心に投資し、カバードコール戦略で安定的にオプションプレミアムを獲得する高配当ETF。
さらに毎月分配型で、直近の分配利回りはおおむね 8〜12%前後。株価の成長と高配当を兼ね備えた「攻めの配当ETF」として、2022年の設定以降、多くの投資家から注目されています。

株価の値上がりは控えめではあるものの、超高配当であるにも関わらず株価も上昇傾向にあります。
JEPQの株価が長期でじわじわ上がる理由
JEPQの株価は長期でみるとじわじわ上昇しています。
その背景にはいくつかの要因があります。
まず、JEPQはNASDAQ100のハイテク株を中心に投資しており、アップルやマイクロソフト、エヌビディア、アマゾンといった成長企業を多く組み入れています。(構成銘柄は後載)
これら企業は売上や利益を着実に伸ばしているため、株価も長期的に緩やかに上昇し、ETF全体の株価上昇につながるというわけです。
さらに、JEPQは保有株に対してカバードコール戦略を採用。
株価が一定の範囲で推移する場合、オプションプレミアムが定期的に収益として加わるため、ETFの基準価額を下支えし、株価が安定的に上昇しやすくなります。
また、毎月分配される配当やオプション収益を再投資することで複利効果が効き、長期保有による株価の緩やかな成長を後押しします。
そこまで大きく上がっていない理由
一方で、JEPQはNASDAQ100に連動するハイテク株ETFでありながら、株価はそれほど大きく上がっていません。
その主な理由は、カバードコール戦略による上昇制限です。
カバードコールでは株価が一定価格以上に上がった場合、オプションを売った分だけ利益が制限されるため、株価の爆発的な上昇は取り込めません。
また、分配金として多くの収益が投資家に支払われるため、ETFの基準価額自体の成長はやや抑えられる傾向があります。
つまり、JEPQは「安定した毎月分配と緩やかな株価上昇の両立」を重視した設計になっており、極端に大きな値上がりは期待できない代わりに、長期保有で着実に資産を増やす運用に適したETFと言えます。
JEPQの年間分配金実績(2022〜2025年)
過去の年間分配金をまとめると以下の通りです。
| 年度 | 年間分配金(ドル) |
|---|---|
| 2022年 | 約 3.85 ドル |
| 2023年 | 約 5.00 ドル |
| 2024年 | 約 5.44 ドル |
| 2025年(途中・9月まで) | 約 4.52 ドル |
表からも分かるように、JEPQは設定以来、年間分配金が徐々に増加する傾向にあります。
2022年の約3.85ドルから2024年には約5.44ドルまで増加しており、2025年も1~9月だけで4.52ドルと前年水準を維持しています。
このように、高利回りを維持しつつ、分配金も少しずつ増やす傾向が見られるため、長期保有する投資家にとっては、毎月のキャッシュフローの安定とともに将来的な増配期待も持てるETFと言えます。
今のところはめちゃくちゃ優秀なETFと言えます。
JEPQの上位構成銘柄(2025年時点)
| 銘柄 | ティッカー | 比率 |
|---|---|---|
| エヌビディア | NVDA | 8.3% |
| マイクロソフト | MSFT | 7.3% |
| アップル | AAPL | 6.9% |
| アルファベット | GOOG | 5.0% |
| アマゾン | AMZN | 4.8% |
| ブロードコム | AVGO | 4.7% |
| メタ | META | 3.5% |
| テスラ | TSLA | 2.7% |
| ネットフリックス | NFLX | 2.6% |
| コストコ | COST | 1.4% |
表を見ると、上位10銘柄だけでETF全体の50%以上を占めており、特にハイテク株の比率が高いことがわかります。
これにより、成長性は高いものの、株価の変動リスクも相応に存在する点には注意が必要です。
私が思うJEPQのメリット
1. 配当金の再投資が楽しい
JEPQは毎月分配型のETFなので、定期的に少額ずつでも配当金が入ってきます。
これを再投資することで、株数が着実に増えていくのを実感できるのが大きな魅力です。
また、どのタイミングでどの銘柄を増やすかを自分で考える楽しみもあります。
まとまった配当金が入るので、銘柄を選べる自由度があるんですね。
(もっぱら私はVYMばかり今は買っていますが…。)
2. 毎月安定して入金がある
月ごとに分配金が支払われるため、キャッシュフローの安定感があります。
生活費の補填や、追加投資資金として計画的に使えるのが魅力です。
毎月「入金がある」という小さな楽しみが、投資へのモチベーションにもつながりますし、長期で保有することで、収入の安定感と資産の増加を同時に感じることができます。
3. 構成銘柄の安心感
先述したようにJEPQの上位銘柄にはアップル、マイクロソフト、エヌビディアなど、長期的に成長が期待できる優良企業が多く含まれています。
ハイテク株はボラティリティがある一方で、これらの優良企業に分散投資することで、一定の安心感を得ながら長期投資が可能です。
銘柄選びに迷うことなく、成長ポテンシャルの高い株をまとめて保有できるのは、JEPQならではのメリットと言えます。
では、配当金生活のシミュレーションを見ていきましょう。
配当金生活シミュレーション(利回り10%想定)
JEPQの高配当を活かして「配当金生活」を実現する場合、どのくらいの投資額が必要かをシミュレーションしてみました。
利回りを10%と仮定すると、生活スタイルごとに必要な資金は大きく変わります。
| 年間生活費 | 毎月の生活費 | 必要投資額(利回り10%想定) |
|---|---|---|
| 150万円(ミニマリスト生活) | 約12.5万円 | 約1,500万円 |
| 300万円(夫婦シンプルライフ) | 約25万円 | 約3,000万円 |
| 500万円(都市型ゆとり生活) | 約41.6万円 | 約5,000万円 |
| 1,000万円(贅沢ライフ) | 約83.3万円 | 約1億円 |
超高配当であるため、仮にJEPQ一本鎗だった場合、少ない資金で配当金生活が実現可能です。
ミニマリスト的な生活なら比較的少額でも配当金生活は可能ですが、都市型のゆとりある生活や贅沢な生活を目指す場合には、数千万円〜1億円規模の投資資金が必要になります。
とはいっても、JEPQ一本で賄うのはリスクが高いため、やはり分散投資で安定性を高めることが現実的です。
JEPQ一本では危険?リスクと注意点
JEPQは高利回りで魅力的なETFですが、投資にあたってはリスクもあります。
まず、NASDAQ100銘柄を中心に保有しているため、相場の調整局面では株価下落幅が大きくなる傾向があります。
また、分配金はオプション収益に依存しているため、毎月の分配額が上下する変動リスクも存在します。
さらに、日本在住の投資家にとっては、配当を日本円に換算する際に為替相場の影響を受ける点にも注意が必要です。
分散ポートフォリオ例(安定性重視)
「JEPQやJEPIに全力投資」は危険。
現実的には多くても全体の20%程度に抑えるのが妥当です。
以下は利回り4〜5%を目指す分散例です。
ちなみに、今回は本記事上での米国株版ポートフォリオ例です。
(日本株はポートフォリオに組み入れるべきだと思います。)
| 投資対象 | 配分比率 | 特徴 |
|---|---|---|
| JEPI | 10% | 安定的な毎月分配 |
| JEPQ | 10% | ハイテク成長+高配当 |
| VYM | 20% | 米国高配当株の王道 |
| HDV | 10% | 財務健全性の高い銘柄 |
| SPYD | 10% | 高利回りの分散枠 |
| VOO | 20% | 値上がり益+分散効果 |
| 債券ETF・現金 | 20% | 暴落・為替対策 |
JEPQやJEPIだけに偏らず、複数のETFや債券を組み合わせることでリスクを分散することが、長期的に安定した配当金生活を実現するポイントです。
特に高成長ハイテク株中心のJEPQは値動きが大きいため、全体の比率を抑えつつ、VYMやHDV、債券などで安定性を補うことで、毎月のキャッシュフローを安定させつつ資産を守る運用が可能になりますね。
まとめ
JEPQは毎月分配・高利回りという特徴から、「配当金生活」を夢見る投資家にとって魅力的なETFです。
しかし、NASDAQ100中心のハイテク株やオプション戦略を組み込んでいることから、単独で運用するのはリスクが大きく危険です。
現実的に配当金生活を目指すには、必要な資金を正しく把握したうえで、VYMやHDV、債券などを組み合わせた分散ポートフォリオを構築することが近道となります。
関連記事
こちらも超高配で話題です。メリットデメリットを整理しています。
ETFばかり買い集める今日この頃。ETFのメリットに関する記事です。